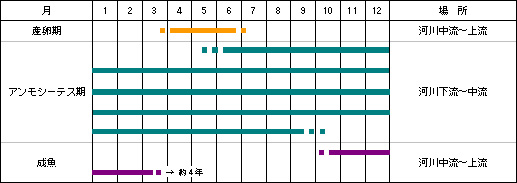| スナヤツメ |
| Lethenteron reissneri |
 |
 |
分 布
北海道、本州、四国と、鹿児島県、宮城県を除く九州に分布する。国外では、沿海州、中国北部、朝鮮半島に分布する。
|
 |
|
|
| 分 類 |
●ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科 |
| 地方名 |
●ヤツメ(近畿地方、四国)、スナクグリ(北陸)、メクラ(関東、新潟、九州)、
スナハマリ、
カゲース(広島県) |
|
 |
| 形 態 |
| 全長13〜16 cm。幼生はアンモシーテス幼生と呼ばれ、吸盤がなく、眼は皮膚の下に隠れる。アンモシーテス幼生の期間を約3年過ごしたのち、全長14〜19 cmで変態する。変態後はいっさい食物をとらない。成体の口は吸盤状で内側に3対の歯がある。眼も体に現れる。消化管は退化して用をなさない。変態後、全長は13〜16 cmに収縮する。 |
| 幼生、成体ともに頭部に7対の鰓穴がある。 |
 |
| 類似種 |
| 太田川には同じ科の魚類は生息していないと思われる。類似種にはカワヤツメ、シベリアヤツメなどがいる。 |
 |
| 生息場所 |
| 幼生・成体ともに、水の澄んだ流れの緩やかな浅い細流に生息する。増水の影響を受けない場所で、湧水のある、砂泥底のところを好む。 |
| 昼間は泥底の比較的浅い場所にひそみ、夜間には活発に泳ぎ回る。降海せず一生を淡水で過ごす。 |
| 太田川では昭和30年代まで本流で多く見られたという。現在では支流の一部に生息する。 |
 |
| 生活サイクル |
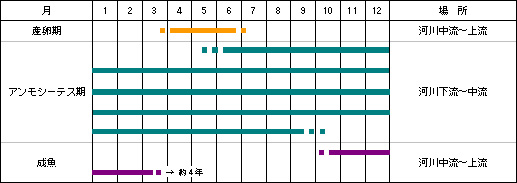 |
 |
| 繁 殖 |
| 産卵期:4〜6月 |
| 産卵場所:生息場所から上流の小川に入り、砂礫底に数尾群がってくぼみを作り、卵を産みつける。 |
| 卵・仔魚:卵は不透明な淡灰色で直径約1 mm。水温19℃、約10日で孵化する。 |
 |
| 食 性 |
| アンモシーテス幼生は、底泥上、底泥中の有機物やケイソウ類をろ過して食べる。
主に水生昆虫を食べる。 |
| 成体は食物をいっさいとらない。 |
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
| ○ |
かんの虫の薬として、マゴタロウ(孫太郎)虫(ヘビトンボ幼生)の代用 となる。 |
| ○ |
生息環境が河川工事や河床の平坦化の影響で、減少している。 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
| 本ホームページ内に掲載の記事・写真などの無断転載・無断引用・販売等を一切禁じます |
| Copyright by 太田川河川事務所 |