| 千代川流域圏会議通信 |
|
|
 |
千代川流域圏会議通信
[2003年10月号 vol.64] |
|
|
|
| [ページ1]
[ページ2] |
| 河川の利用には許認可が必要なことがあります。 |
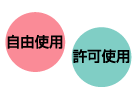 川はみんなの財産なので、水泳、魚つり、散策、サイクリングなど他に迷惑をかけない一般的な用途であれば誰でも自由に利用することができます。但しキャンプや物干し場などに使う時には、前もって国土交通省の各河川出張所に届け出が必要です。また工作物を新築したり土地を掘削したりする行為などは、河川の効用に影響を及ぼす恐れから原則として禁止されていますが、特定の申請に基づいて河川管理者の許可を得た上で河川使用が認められる場合があります。さらに特許使用といって、土石や砂利の採取、土地の占用、流水の使用など特別に使用権を設定することで初めて河川使用が可能となるケースもあります。 川はみんなの財産なので、水泳、魚つり、散策、サイクリングなど他に迷惑をかけない一般的な用途であれば誰でも自由に利用することができます。但しキャンプや物干し場などに使う時には、前もって国土交通省の各河川出張所に届け出が必要です。また工作物を新築したり土地を掘削したりする行為などは、河川の効用に影響を及ぼす恐れから原則として禁止されていますが、特定の申請に基づいて河川管理者の許可を得た上で河川使用が認められる場合があります。さらに特許使用といって、土石や砂利の採取、土地の占用、流水の使用など特別に使用権を設定することで初めて河川使用が可能となるケースもあります。 |
| 原則として許可できないもの |
●必要性の認められないもの
●営利を目的とするもの
●河川敷地の占用で公共性のないもの
●治水上支障となるもの
●その他河川管理上不適当なもの
 |
|
| 特別使用では |
許可使用
●工作物の新築、改築、除去(河川法第26条)
●河川敷地の形状の変更(河川法第27条)
●河川における竹木の流送または舟や筏の運行(河川法第28条)
●その他河川の流れの方向、清潔、流量、幅員または深浅などについて、河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為(河川法第29条)
特許使用
●河川の流水の使用(河川法第23条)
●河川区域内の土地(国有地)の占用(河川法第24条)
●河川区域内の土地(国有地)における砂利などの採取(河川法第25条) |
|
|
|
| 鳥取大地震から60年 |
昭和18(1943)年の鳥取大地震から、今年で60年がたちました。この地震の被害規模としては、死者1,210人、負傷者3,860人、全・半壊家屋が27,405という資料が残っています。
この地震では夕方5時36分過ぎという時間でもあり、夕食の用意のためのガスの使用が多かったため火災などの2次災害が多かったと言われています。
地震がおきたら
●まずわが身の安全を図る
●すばやく火の始末
●非常脱出口を確保する
●火が出たらまず消火
●門や塀に近寄らない |
|
| 千代川あれこれ<浜坂町の供養塔> |
 寛政7(1795)年、近世における鳥取藩内で最大の死傷者を出した乙夘洪水がおきました。この洪水では千代川水系の被害が甚だしく、「因府年表」によれば、「円通寺と国安の土手が決壊して、水が城下へと奔流のごとく流れ込んだ」といいます。そして、幕府への届け出では死者が670人にのぼったとのことです。 寛政7(1795)年、近世における鳥取藩内で最大の死傷者を出した乙夘洪水がおきました。この洪水では千代川水系の被害が甚だしく、「因府年表」によれば、「円通寺と国安の土手が決壊して、水が城下へと奔流のごとく流れ込んだ」といいます。そして、幕府への届け出では死者が670人にのぼったとのことです。
この死傷者を供養するため、当時千代川河口に面していた浜坂村(当時)に「溺死海会塔」が建てられました。現在ではあまり人目のつかない場所となっていますが、当時の洪水が引き起こした悲劇を今に伝えています。(参考:鳥取県史) |
「千代川をより良くしたい」「流域をもっと元気にしたい」
千代川流域圏会議では平成16年度賛助会員を募集しています |
鳥取県東部を貫流する「千代川」は流域住民の生活を支え、命を育んできました。この千代川の清流を次世代に引き継ぐため、千代川流域圏会議では「清流を守る行動計画」を策定し、数々の活動を実施しています。
この清流を守る行動計画を実行する際に、多くの流域の皆様に千代川の清流について関心を持っていただくとともに、皆様による行動の参加がありますと、清流を守る行動をより充実させることができます。
つきましては、当流域圏会議では賛助会員を募集いたしておりますので、趣旨に賛同していただける方は、ご加入いただきますようお願い申し上げます。
千代川流域圏会議 会長:道上 正規
年会費:賛助会員(個人)1,000円 (団体)10,000円
|

千代川フェスティバル'03が盛況のうちに終わりました。途中、雨がふりだしたりと残念なところもありましたが(終わってからのスコールがまた凄かった!)、皆さんの笑顔と歓声でいっぱいの楽しいイベントになりました。
今回初お目見えの「清流君バルーン」はいかがでしたか?(来られなかった人は1ページ目の写真を見てね)このバルーンはこれからも千代川フェスティバルなどの機会に、千代川流域圏会議のシンボルとして上げていこうと思っています。 |
|
|
|