| [to TOP] | |
|
|
|
|
平成12年8月24日 |
|
庚午・観音高架橋、新旭橋コンクリート調査結果のお知らせ
 1.庚午・観音高架橋、新旭橋のコンクリート調査結果
①剥離の状況 床版コンクリートの剥離箇所(調査段階でたたき落とした箇所を含む)は、床版面積の約1%となっていました。剥離箇所は、庚午・観音高架橋では、鋼製桁の橋については張り出し部、コンクリート製桁の橋については桁と桁の間の間詰め部に多く見られました。また、新旭橋では張り出し部や橋脚に挟まれた中央部に多く見られました。 ②コンクリートの状況 a.強度 シュミットハンマー試験※3による推定圧縮強度は、240~310kgf/cm2の範囲にあり、平均300kgf/cm2となっていました。また、現地で採取したコンクリートコアの圧縮強度試験※4による圧縮強度は、235~410kgf/cm2の範囲にあり、平均320kgf/cm2となっていました。 b.その他物性 ・中性化※5を示す深さは、コンクリート表面から15~35mmの範囲にあり、平均22mmとなっていました。 ・コンクリート中の塩分含有量※6は、0.4~3.6kg/m3の範囲にあり、平均1.6kg/m3となっていました。 ・アルカリシリカ反応性試験(化学法)※7による骨材の判定では、多くの箇所がアルカリ反応性に対し「無害ではない」と判定されました。 (3)考察 ① コンクリートの表面剥離は、コンクリート中の鉄筋が腐食することにより、その体積が膨張し、その膨張圧によりコンクリートにひび割れが生じて発生したものと考えられます。鉄筋腐食は、コンクリートの中性化の他、飛来塩分、含有塩分といった要因が複合して発生し、特に、組立て鉄筋※8がある箇所など、鉄筋のかぶり※9不足が考えられる箇所において、表面剥離が生じたものと考えられます。 ② コンクリートの中性化については、時間の経過とともに、コンクリート表面から空気中の炭酸ガスと水分が徐々に吸収され、現在の状況にまで進行したものと考えられます。また、コンクリート中の塩分については、施工当時に海砂を十分に洗浄せずに用いていた可能性や瀬戸内海からの飛来塩分の影響から、含有されたものと考えられます。 ③ 中性化深さ、塩分含有量と表面剥離の関係については、今回の調査データでは明確な相関関係は認められませんでした。 ④ アルカリ骨材反応※10については、化学法によりアルカリ反応性骨材の存在が認められましたが、アルカリ骨材反応によるひび割れは、ほとんど認められませんでした。 2.対 策(補修・補強) 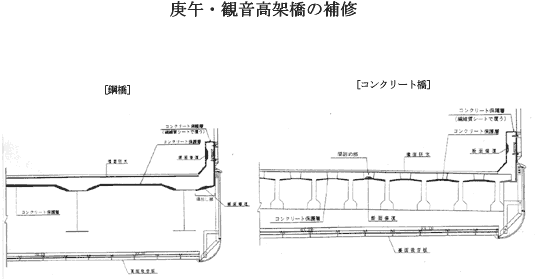 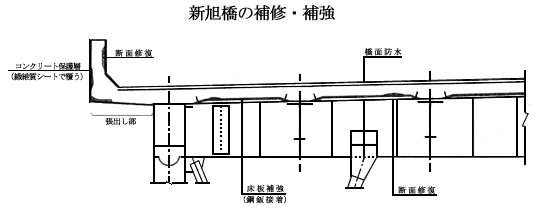
現在、対策の基本方針を踏まえ、詳細な設計を進めているところであり、この設計がまとまった段階で、補修・補強工事に順次着手していく予定です。今後、速やかに鉄筋防錆と断面修復の工事に着手し、平成15年春までには全体の補修・補強工事を完了する予定です。 なお、この工事完了までのコンクリートの剥離落下に対しては、はがれ落ちそうな箇所は既にはつり落としていること、高架下の全面に板張り防護工を設置していることから、街路部の通行には問題がないものと考えています。
〔参 考〕 1.西広島バイパス都心部延伸事業について (1)経緯 西広島バイパス(2号高架)都心部延伸は、広島南道路との役割分担を考慮した上で、広島西部地域からの交通を都心部に円滑に分散・導入させるものとして、平成6年8月に都市計画の変更を行いました。 その後、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災を教訓とした、高架道路の1本柱橋脚の補強工事を最優先に進め、昨年12月に、この補強工事が完了しました。 その後、全線完成に向けての第1歩(1期区間)として、平成10年度より、庚午から新観音橋東詰めまでの間約2.1kmについて、2号高架の4車線化及び延伸工事に着手することとしました。現在、南観音地区において橋脚補強工事、観音本町地区において延伸区間の橋脚工事を進めています。
(2)整備効果 ○渋滞緩和 ○沿道環境の改善 (電線類地中化、歩道美装化、遮音壁・低騒音舗装の整備等) (3)観音高架橋の経緯
2.コンクリート調査 用語説明 ※1 床版、壁高欄(新旭橋の例) 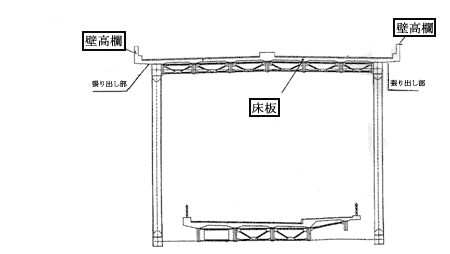 ※2 板張り防護工 作業用足場及び作業中の落下物防止のため床版下に設置した防護工です(表紙写真を参照)。 ※3 シュミットハンマー試験 コンクリートを破壊しないで強度を推定する方法で「シュミットハンマー」という測定機材を使用して試験を行なうものです。コンクリートに鋼球を打ちつけると、強度が大きいコンクリートは、鋼球の反発度が大きく、強度の小さいコンクリートは鋼球の反発度が小さいという特性を利用し、コンクリート表面を打撃し、その反発硬度を測定して間接的にコンクリートの強度を推定します。 ※4 圧縮強度試験 コンクリート試験体を圧縮試験機によって徐々に上下から力を加えると、試験体にひび割れが生じ、やがて壊れてしまいます。圧縮強度はこの時の力の大きさを試験体の断面積で割って算出します。 ※5 中性化 コンクリートは本来アルカリ性ですが、年月を経るとともに、表面から徐々に空気中の炭酸ガスと水分を吸って、セメントの成分と反応してそのアルカリ性を失っていき、中性化していきます。 コンクリートの中性化の度合いを試験する方法として、コンクリート表面にフェノールフタレイン溶液を小型の噴霧器を用いて吹き付け、紅色に変色するかどうかを調べ、変色しなかった厚さを測定し、これを中性化深さとしています(※フェノールフタレインはアルカリ性で紅色、中性で無色になるという性質を持つ試薬です)。 ※6 塩分含有量 コンクリート中に含まれる全塩分量のことで、採取したコアを細かく粉砕したものを強酸で溶解し、塩分以外の不純物を沈殿させた上で、上澄み液に試薬を加え、全塩分量を算出します。 ※7 骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法) コンクリートから取り出した骨材をアルカリ溶液中で反応させ、骨材のアルカリ反応性を短期間に判定する試験方法です。判定は「無害」「無害ではない」のいずれかとなります。 ※8 組立て鉄筋 構造上は必要ありませんが、鉄筋を組み立てた後、配置するまでに緩まないようにするために用いられる鉄筋です。 ※9 鉄筋のかぶり 鉄筋の腐食を防ぐ等の目的で、鉄筋をコンクリートで十分に包んでおく必要があり、鉄筋の最外面からコンクリート表面までの距離を「かぶり」といいます。 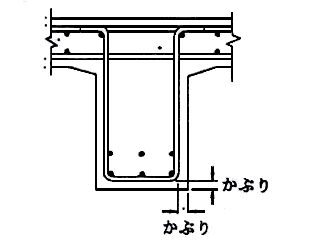 ※10 アルカリ骨材反応 コンクリート中のアルカリ成分が、反応性の非晶質シリカ(二酸化ケイ素)と化学反応を起こし、水分を吸収することにより、コンクリートが異常膨張し、ひびわれが発生する現象を「アルカリ骨材反応」と呼んでいます。 ※11 特殊なモルタル ひび割れが生じにくい、密実なモルタルです。なお、モルタルとはセメントに水と細骨材(砂)を混ぜたものです。 ※12 鋼板接着工法 コンクリート構造物に板状の鋼板を接着することにより既設コンクリートと一体化する補強工法です。併せて、水と空気の遮断もできます。 ※13 裏面吸音板 高架下を走行する自動車騒音の反射音を低減するための吸音板で、高架橋の下側に取り付けるものです(完成予想図を参照)。 |
|
|
||
| [当資料に関するお問い合わせは] 国土交通省 中国地方整備局 広島国道工事事務所 TEL (082)281-4131 FAX(082)286-7897 E-mail Address:hirokoku@cg.moc.go.jp |
||