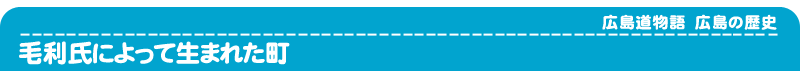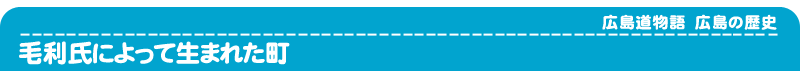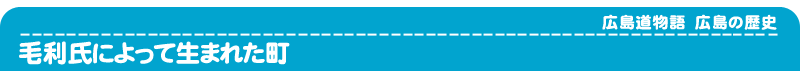
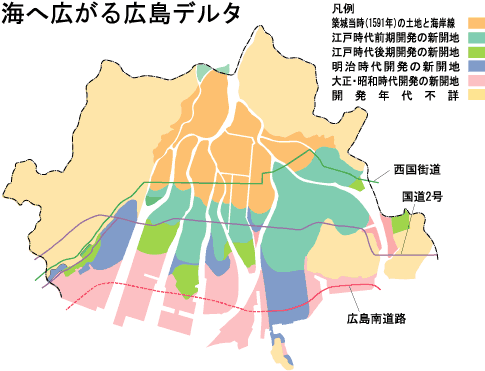 |
16世紀の半ば、安芸の国の小豪族から全国屈指の戦国大名にのし上がり、中国地方の大半を支配した毛利元就。吉田の郡山城を拠点にしていた彼は、勢力が広がるにつれ、水上交通の便のよい沿岸地域への進出を考え始めました。そこで目を付けたのが、当時五箇庄と呼ばれる寒村だった太田川河口デルタ、つまり現在の広島です。太田川流域から広島湾一帯は、律令時代から陸上交通の幹線道路である山陽道、中国山地と沿岸部を結ぶ太田川河川交通、瀬戸内海の海上交通の接点であり、その軍事的・政治的・経済的な意義に着目したのです。
元就の死後、その夢を果たしたのが孫の毛利輝元です。輝元は豊臣秀吉が全国を統一する前年の天正17年(1589年)、佐東川(現・太田川)河口の中州に築城と城下町の建設に着手。世に"島普請"と伝えられるほどの多大な労苦の末、わずか2年足らずという驚異的なスピードで、中国地方屈指の大都市が姿を現しました。これが広島の始まりで、このとき「広島」と命名したのも輝元です。
彼はデルタを埋め立て、多くの新開地の干拓を押し進めるとともに、城下町の街路を碁盤目状に整え、領国内外を結ぶ街道の整備に力を入れました。広島は、毛利氏の後、福島氏、さらに浅野氏の時代も干拓が進められ、城下町として、また中・四国地方における交通・経済の中心として発展していきますが、広島の町づくりの基礎は輝元の時代に確立されたといえます。 |
|
|
↑このページの上へ戻る | ↑広島の歴史トップへ戻る