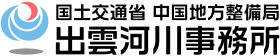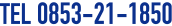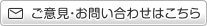水質用語
水質を評価するためのものさしについて解説します。
- 透明度※
- 水の濁りの指標。直径25~30cmの白い丸い板(セッキー円板)を水中に沈めていって、その板が見えなくなるまでの深さ(m)で表す。透明度は水中に浮遊している物質(泥やプラクトン)の量によって決まる。風が強いときや大水のあとでない限り、プランクトンの量に左右される。
- 水素イオン指数(pH)※
- 水溶液中の水素イオン濃度[H+]の逆数の対数で表す。植物プランクトンが繁殖するような湖沼では、上層で高いpH値を、下層で低いpH値の低いpH値を示すことが多い。一般に、上層のpH値の上昇は光合成による溶存CO2の減少に、低層でのpH値の低下はプランクトンの遺骸等がバクテリアにより分解されて生成するCO2や有機酸に起因する。
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
- 水中にある有機物を、微生物(バクテリア)が分解する時に消費する酸素の量を示し、河川の汚濁を表す場合の代表指標として使用される。 一般的に数値が大きくなれば、水中に有機物が多く、水が汚濁していることを意味する。 水道の原水としては、3mg/リットル以下であることが望ましく、魚では汚濁に強いコイ・フナ類でも5mg/リットル位までが限度で、河川環境の立場からは4mg/リットル程度までが望ましい
- 化学的酸素要求量(COD)※
- 水中の被酸化物質、主として有機物を酸化剤によって酸化するときに消費される酸素の量。汚濁の指標で、とくに有機物量の相対的な尺度として用いられる。
- 水中懸濁物質(SS)※
- 試料水をろ過、または遠心分離によって分離される物質をいい、通常、105~110℃で2時間乾燥した後の重量をもって表す。
- 溶存酸素量(DO)※
- 水中に溶解している酸素、清澄な河川水では飽和量に近いが、下水など有機物の多い水は分解のため消費されて少ないのが通例。植物プランクトンの繁殖している湖沼の上層では、光合成による酸素の生成のためしばしば過飽和を呈する。溶存酸素の欠乏は魚介類のへい死等を招くことがあるのでその重要な指標となる。
- 大腸菌群数
- 大腸菌群数には、大腸菌および大腸菌と性質が似ている細菌の数をいう。 し尿汚水の指標として使われている。 大腸菌群数の数値は、検水100ml中の最確数(MPN)で表しているが、最確数とは「この位だ」という数字である。
- 窒素(N)※
- 窒素は植物プランクトンの増殖に不可欠な元素で、有機態窒素と無機態窒素に大別される。一般に、栄養塩として植物プランクトンに摂取されるのは主に無機態窒素である。
- リン(P)※
- リンも窒素同様植物プランクトンの増殖に不可欠な元素で、有機態リンと無機態リンに大別される。一般に栄養塩として植物プランクトンに直接利用されるのは無機態リンである。 栄養塩は、主として集水域から河川を通じて流入(外部負荷)と湖底泥からの回帰(内部負荷)により供給される。
- 富栄養化
- 湖沼やダム湖などの水の出入りや交換が少ない水域において、窒素やリンなどの栄養塩類の濃度が増加することをいう。特に、肥沃な土壌や人間活動が盛んな地域の下流の上記のような湖などでは、豊富な栄養塩類が流入してくるために富栄養化が進み、藻類が大量発生し、水の華、淡水赤潮などとよばれる現象がおこる。
- クロロフィルa※
- 植物プランクトン量の指標。クロロフィルは光合成に不可欠な緑色色素で、a,b,c,d,の4種類に分類される。クロロフィルaは全ての藻類に含まれ、クロロフィルbは緑藻類、クロロフィルcは珪藻、渦鞭毛藻類に含まれる。
- 塩分※
- 海水1kg中に含まれる塩類のグラム数。宍道湖・中海のような汽水湖の水質を論じる場合には不可欠な水質項目。塩分の代わりに塩素量(海水1kg中に含まれる塩素・臭素およびヨウ素の全量をグラム数で示したもので、臭素・ヨウ素は当量の塩素で置き換えられているものとする)もよく用いられる。
- 環境基準
- 国や地方公共団体が公害防止対策を進めるために、環境の質をどの程度のレベルに維持しておくことが望ましいかという目標値をいう。 環境基本法によって、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音について定めることとされている。 水質汚濁に係る環境基準は平成11年に改正され、人の健康の保護に関しては26項目・生活環境の保全に関しては、河川5項目・湖沼7項目・海域7項目の基準が定められている。 斐伊川本川は河川AA類型、宍道湖・中海は湖沼A類型Ⅲ。
※は、高安克己 編『汽水域の科学』講師グループ著『汽水域の科学 中海・宍道湖を例として』「3章 汽水域の水質特性(島根大学総合理工学部 清家 泰)」より引用