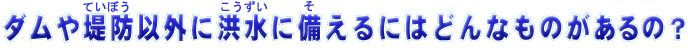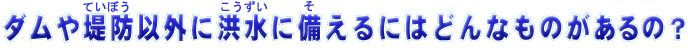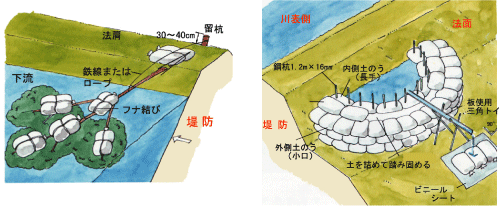大雨が降ると、山間部のダムは洪水をためて下流に流れる水の量を少なくし、堤防は流れてきた洪水をあふれないように安全に流そうとします。しかし、土でできた堤防は、モグラの穴があっただけでも水が漏れ危険な状態になることもあります。こうしたときに、風雨の中を現地に行って堤防の補強を行ったりするのが「水防」であり、ダムや堤防などの洪水防御施設とともに洪水被害を小さくする重要な役割をもっています。
水防工法の代表的なものには、「木ながし」と「月の輪」があります。「木ながし」は洪水流が堤防を表面から崩そうとする力を分散(弱める)働きをし、「月の輪」は、堤防にしみ込んだ水を抜き出すことで、堤防の中から崩そうとする力を弱めようとするものです。 |