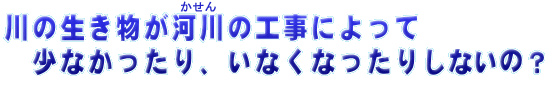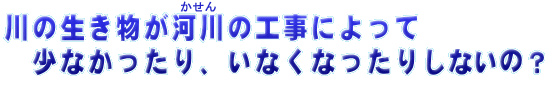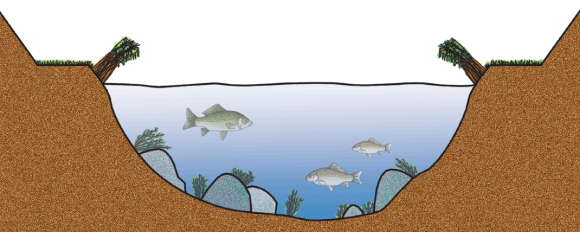河川工事が行われた後の川では、魚の数が減った、種類が少なくなった、あるいは水鳥がいなくなった、などという話をよく聞きます。極端な例として、農業用水路などでみられる「三面張り」といわれる両岸と川底の三方を全てコンクリートで固めてしまったような川では、ほとんどの生物が激減するといわれています。
これまでの河川工事では、洪水被害の防止や人間の利用が優先され、川の生き物の生息環境が失われることも少なくありませんでした。現在では、生態系に悪い影響を及ぼすような河川工事のやり方を反省し、生き物とその生息環境を守りながら、河川工事を行う方法が試みられており、代表的なものに「多自然型工法」があります。 |