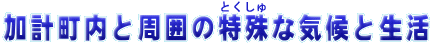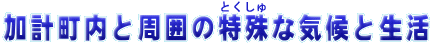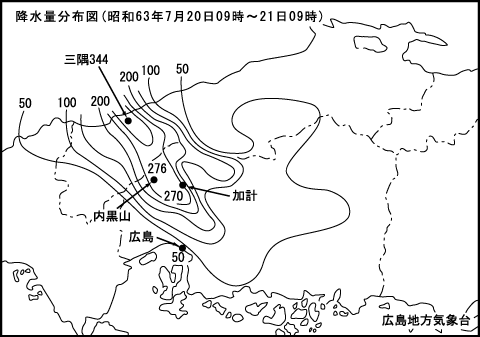昭和63年(1988)7月の梅雨末期豪雨は、加計町だけで11名もの死者をだしました。この年の7月15日、総雨量200ミリを超えたのは浜田市(359ミリ)を中心として東西約40km、南北約25kmと狭く、浜田から15キロ足らずの三隅町では96ミリどまりでした。それが20〜21日には総雨量200ミリ以上の強雨域は、三隅町から加計に至る幅20km、長さ45kmという帯状に広がりました。総雨量の9割が4時間に降るという驚くべき集中ぶりでした。このように島根県から広島県北西部にかけて襲った集中豪雨は、昭和30年以降だけでも、33年、39年、47年、58年、60年、63年と6回も起きています。
本来、日雨量が200ミリ以上の豪雨が起こりやすい地域としては、九州中南部と四国、紀伊半島の南東側、伊豆半島などがあります。日本海側ではあまり強い豪雨は発生していないのですが、唯一の例外がこの山陰西部から広島県北西部にかけてなのです。
●昔の言い伝え
広島県山県郡芸北町には次のような言い伝えがあります。
「(町の西部にある)八幡が降るときは(島根の)三隅が大雨。(町の東部の)大暮の大雨は、浜田から来る」
豪雨が谷や山の地形の並びに沿って動くことを、昔の人たちは肌で知っていたと言うことです。 |