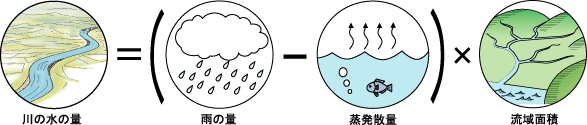日本の年降水量は、地域的な差はありますが、平均すると1,714mmであり、世界の年降水量の平均値約970mmの2倍近くに達します。地上に降った雨はやがて川に流れ込み、一部は大気中へ「蒸発散」し、一部は地下へ「浸透」します。この地下に浸透した水は、地下水のまま海へ流れていくものもありますが、大部分はゆっくり川へ流れ出しています。このため、川の水量は、次のように表わすことができます。
川の水量=(降水量-蒸発散量)×流域面積
日本ではおおよそ、年間の降水量1,714mmのうち、蒸発散量は約600mmですから、国土面積37.8万km2についてみますと、
(1,714mm-600mm)×37.8万km2=4,200億m3
が1年間に川を流れる水(一部は地下水)ということになります。
なお、降水量に対して、川に流れ出る水量の占める割合を「流出率」と呼んでいます。日本の場合の平均的な流出率を計算してみれば、
(1,714mm-600mm)÷1,714mm≒0.65
となりますが、これも川によって大きな差があります。 |