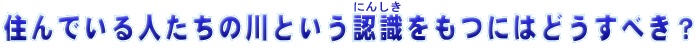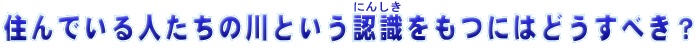昭和30年代初めの日本各地の「いなか」では洗濯や食器などの洗い物をするために川に近づきながらも洪水の時には川から避難しました。現在では、川は河川管理者である国や自治体によって、管理されたことにより、上水道は完備され、川はコンクリート護岸で改修され、あふれることも少なくなりました。しかし、水道をひねれば蛇口から水を得ることができるようになり、地域の人々と川の関係が薄くなって、人々は川への関心をなくしてしまいました。
近代化した生活のなかで、かつてのような川との関係を取り戻すことはむずかしいことですが、河川管理者が洪水防御も環境も全ておこなうというのには限界があります。美しい川を守り、洪水、地震などの非常時のみでなく、川に接する自分たちの生活環境を守るためには、まずは住んでいる人たちが、この川は自分たちの川だという意識をもつことが重要であり、川との新たな関係づくりが必要となっています。 |