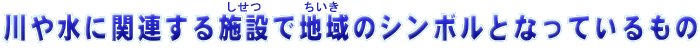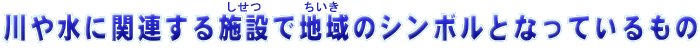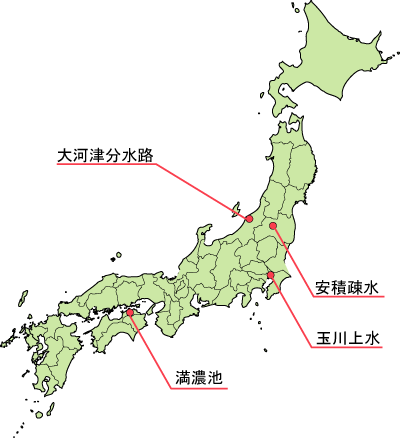●満濃池
日本でも、古来よりかんがい用の溜池ダムがつくられていました。 821年に空海によって修築されたといわれる香川県の満濃池ダムは、高さ32m、長さ155mで溜池としては日本最大規模の大きさを誇っていて、10世紀以上たった現在でも貯水池として使用されています。
●玉川上水
玉川上水は、徳川家康が幕府を開いてから50年後の承応2年、西暦1653年につくられました。
●安積疎水
猪苗代湖から山を貫いて福島県安積地方に通水するため明治維新期に作られたものです。
●大河津分水路
明治42年(1909)から大河津分水工事は、政府の直轄工事として本格的に始められ、13年の歳月と、廷べ1,000万人の人手を費やして、大正11年(1922)に通水しました。 |