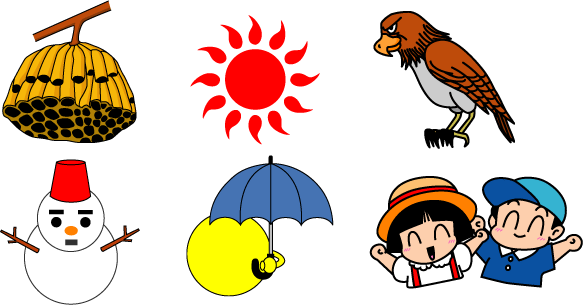加計町など広島県内陸部に古くから言い伝えられてきたことわざのうち、天気や災害に関するものを紹介します。
「蜂の巣が低いと台風が多い」
台風の強風を避けるためにあらかじめ低いところに巣をつくる蜂の習性から、長期予報ができると言うことです。
「寒中の雷は夏日照り」
冬に大陸の高気圧の威力が強い年に夏に日照りになりやすいということです。
「鳶が舞うと雨」
雨雲をもたらす上昇気流に乗って鳶などが空を舞うので雨が降るということです。
「こうぞうの葉の厚い年は大雪」
その夏の成長の良い年の冬は大雪になりやすいということです。ゴマの実入りの良い年は大雪、麦の芽だしの足の長い年は大雪などという地域もあります。
「月が傘をさすと雨、傘の中に星が見えると晴れ」
傘をさした月とは「おぼろ月夜」のことで、温暖前線や低気圧が近づくと、すじ雲(絹雲)がまず発生し、次にうす雲(絹層雲)が現れ、次第に低い雲となり雨が降り始めます。一方、傘の中の星というのは、星のまばたきを意味しています。これは、空気の波動が激しいときにみられ、移動性高気圧などの前面から中心近くにおける天気を表しています。
「子供の長遊び、明日は雨」
「夕方、子供がはしゃぐと雨になる」という地方もあります。低気圧が近づき雨になる前日は、一般に南風が吹いて暖かいので、子供は陽気にルンルン気分になるという。しかし、暗くなるまで遊ぶのは危険などもともなうので、早く帰宅するようにという、戒めとも考えられます。 |