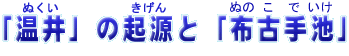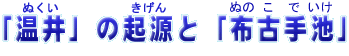昔々、温井の里に大窪(または大久保)というところがありました。そこの岩間から、温かい水が湧き出ていたそうです。村人たちは、いつもこの湯を使って、傷の治療や、足腰の痛みをなおしていました。その効き目は近所の村々に言い伝えられて、湯治の客も多くなるばかり。周囲からこの里を、温かい井戸「温井」と呼ばれるようになったということです。
ところが、湯元から50間下流に、幅10間・長さ20間の大きな沼があり、底なしの沼ともいわれていたが、その沼には、日暮れになると、どこからともなく1人の老婆が現れて、夜な夜な布をさらしている、という噂が誰いうともなく広がって「あそこへ夕方行くと、布古手婆が出てきて、子どもをさらって行くそうな」と、みんなから恐れられるようになった。それからは、湯に来る客も全くなくなったということです。
そこで地主は、この沼を埋め立てて田畑を作ることにして、まわりの人たちに頼んで、4、5年かけて完成させて、そこに氏神さまも祀り、翌年、その田に稲を植え付け、まわりの人たちを皆呼んで、開田の祝いもしたそうです。
稲は順調に育ち、これで秋の取り入れを待つのみ。このぶんなら今年は大豊作、とたいへん喜んでおったところ、9月に入ると急に天候が崩れ、降るわ降るわ、今でいう集中豪雨に見舞われ、荒れ狂う滝山川の大洪水に、田畑は見る見るうちにのみ込まれてしまい、翌日になってみると、もとの田畑は白い河原となっていました。そして、温井の温かい水も冷泉となってしまいました。
でも、布古手池はもとのところに元通りできていたということで、これは布古手池の祟りだと、末永く語り継がれ、以来この沼に誰も手をつける者は無かったという話です。 |