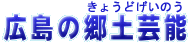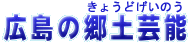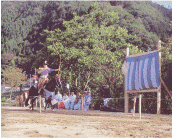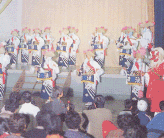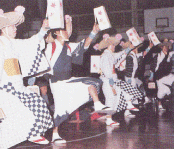●湯立神楽(広島県無形民俗文化財)
江戸時代中期以前(正徳年間)から長尾神社に伝承されている湯立神楽は、祭祀の前に湯立ての神事を行い、つづいて湯立ての舞を奉納するという他にあまり類例のないものです。
●加計げんこつ踊り(加計町無形民俗文化)
丁川地域に伝承されているげんこつ踊りの元祖は、江戸時代(安正年間)に虫送り行事で踊った「豊年踊り」とも「鳥追い踊り」ともいわれています。「げんこつ」の名の由来は踊り子の右手に鳴子を打ち鳴らす所作からという説、明治の凶作に麻の2度蒔の成功に喜んだ若者たちの乱舞の様子かという説の2つ説があります。
●津波太鼓踊り(広島県無形民俗文化財)
津浪地域に伝承されている太鼓踊りの歴史は古く、天正9年(1951年)出雲の国に神田福一という人から伝授されたと、江戸時代後期(文化年間)の記録にあります。元来は稲の害虫を追い払う虫送り行事の際に田の畔で踊られた「豊年踊り」が原型で、その後「祝賀の踊り」になったと考えられています。
●流鏑馬神事(加計町無形民俗文化財)
堀八幡神社に伝承されている流鏑馬は、中国地方でも珍しく、古い伝説やゆかりの地名を残しており、江戸時代以前からの伝承と考えられています。
●殿賀田楽(加計町無形民俗文化財)
田楽は昨今は田植え行事から離れましたが、田仕事が一段落してから行われていた豊作を祈願する「囃子田」が原型です。加計町内各地域で行われていましたが、現在伝承されている地域は、殿賀地域と安野修道地域の2カ所です。 |