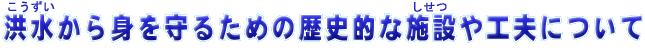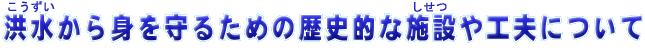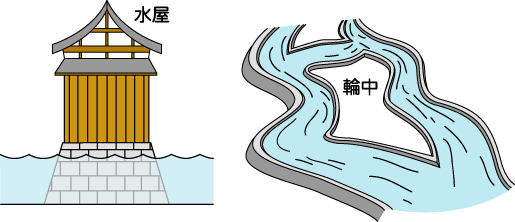むかしの人々が洪水から身を守る工夫をしてきたものには、「水屋」と「輪中」といったものがあります。
●水屋
水屋は、屋敷内に石垣を高く築いて、その上に建物を載せたものです。石垣の高さは洪水時にも水がつからないように3〜5m以上に及び、建物には非常用の米や味噌などの食料のほか、生活用の雑貨を保管して長期の洪水でもしのげるようにしました。
●輪中
輪中は、水屋が家族単位の水防対策であるのに対して、地域ぐるみで水害に対処したものです。たびたびの水害による農作物の被害を防止し、また、地域の生活を守るために、地域全体を堤防(輪中堤)でかこい、周辺が浸水しても堤防内側の集落や農地は、浸水をまぬがれたのです。 |