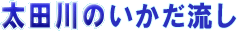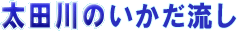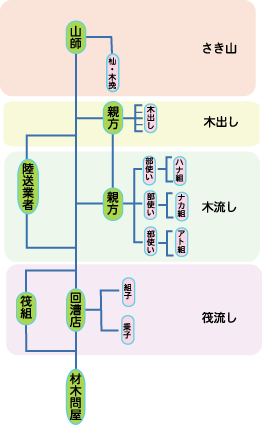丂懢揷愳偺敵棳偟偑偄偮崰偐傜巒傑偭偨傕偺側偺偐偼柧傜偐偱偼偁傝傑偣傫偑丄柧帯屻敿埲崀丄揝摴偺枍栘偲偟偰戝検偺栘嵽偑塣斃偝傟偰偄傑偟偨丅傑偨丄揹拰嵽丄寶抸嵽丄儅僗僩偦偺懠偺慏敃梡嵽丄僇僉梴怋梡偺抾側偳偑敵棳偟偝傟偰偄傑偟偨丅
丂栘嵽偺塣憲偼丄栘嵽偺敯嵦偐傜敵棳偟傑偱傪堦楢偺峴掱偱峴傢傟偰偄傑偟偨丅
丂丂丂丂丂嘆偝偒嶳仺嘇栘弌偟仺嘊栘棳偟仺嘋敵棳偟
丂嘆偺偝偒嶳偼嶳巘偲屇偽傟傞栘嵽嬈幰偑攦偭偨嶳傊瀃偲栘斠偑擖偭偰敯嵦丒惢嵽偡傞偙偲偱丄敯嵦偟偨栘嵽傪嶳偐傜愳偵擖傟傞抧揰傑偱乽僔僟乿傗乽僪僌儖儅乿乽僪價僉乿乽僉儞儅乿側偳偺庤抜偵傛偭偰塣傃弌偡偙偲傪栘弌偟偲尵偄傑偡丅嘆偲嘇傪偁傢偣偰嶳弌偟偲傕尵傢傟偰偄傑偟偨丅嶳弌偟偼壞偺偆偪偵峴偄栘棳偟傪廐傑偨偼弔偺愥偳偗悈偵偺偣偰昹傑偱塣傃傑偟偨丅 |