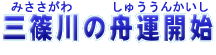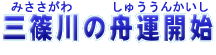| 毛利氏時代には、広島河口を基点に可部(可部町)・下深川(高陽町)あたりまで舟運があり、広島城築城には大いに助かりました。福島氏によると上深川(高陽町)まで舟路を延長し、引き続き上流の開作を考えましたが、工事に難所が多く容易でないことから工事はとりやめとなりました。けれども奥地の年貢米や鉄などの輸送には、川舟利用が是非とも必要でした。そこで、浅野氏は寛永九年(1632)に川船が通れるか水路を調べ、最大の難所は3〜5尺も落差のある岩淵とどろきの瀬(白木町)であることがわかり、この脇に新しい川を掘って舟を上流まで通れるようにしました。 |