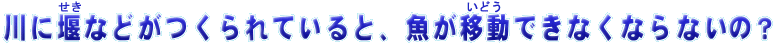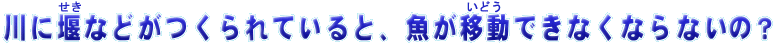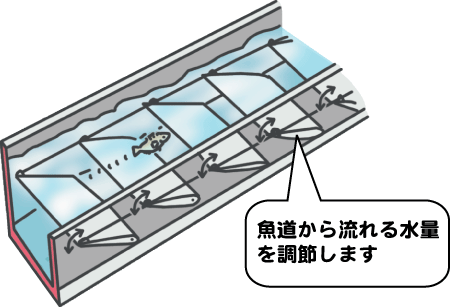| 川のなかには、治水(洪水被害の軽減・防止)や利水(農業・工業・水道用水の取水など)を目的として、ダムや堰など川の流れを遮断する人工的な施設がつくられることがあります。「河川横断工作物」と呼ばれるこれらの施設は、川のなかを行き来する魚からみれば、水域間の移動を妨害する、いわば“迷惑施設”になります。このような魚にとっての“迷惑”を少しでも軽くするために、堰などには一般に「魚道」が設置されています。本来、魚には水流に逆らって泳ごうとする性質(これを「走流性」という)があります。そのため、河川横断工作物に適当な魚の通れる道をつくり、魚の走流性を利用して上流側へとうまく導いてやることが魚道の役目なのです。 |