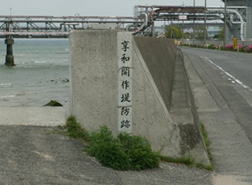| 榺池神社 (ちきりいけじんじゃ) |
 |
厳島神社の祭神、市杵島姫命が筑紫から安芸へ移って来る時、
木野川を渡り苦の坂へさしかかりました。
2才の幼子を背負っているので息もきれぎれになり、「えらや
苦しやこの坂は、鉄のちきりもいらぬもの」といって、手に持っ ていたちきり(機織りのたて糸を巻く鉄の棒)を麓の池に投げすてて しまいました。
後に池を埋め社を建て、女神を祀ることになりました。
これが榺池神社である。
|
| 汐 湧 石 (しおわきいし) |
 |
|
榺池神社の境内に穴のあいた石があり、この穴の中に毎年厳島
神社の管弦祭の日である6月17日(旧暦)夜、海水が湧き出る
という。
|
| 苦 の 坂 |
 |
|
この坂は木野川沿いの木野2丁目と防鹿の境付近から山側へ
4町9間(約 452㍍)の急坂をもち、古くから大河原山、立戸山
とともに防長に対する先陣の適地として注目されていた。
|
| 太閤振舞い井戸 |
 |
|
古くからある湧き水で、湧き出る水の量が多く、干ばつでも
水が枯れることをありませんでした。
そして、飲み水、かんがい、紙すき、防火用水として広く使
われていました。
文禄・慶長(1592~1597)の役で九州名護屋城に、太閤秀吉は
二度陣頭指揮のため往復した記録がある。
その折りの伝承として、秀吉軍が山陽道木野路通過の折り、
村人たちがこの井戸の水でお茶を点て差し出したところ、大変
ご満喫されたと伝えられている。
|
| 両 国 橋 |
 |
|
大正6年小瀬村と木野村の有志組合により初めて木橋が架け
られました。
周防・安芸両国にまたがることから両国橋と名付けられ、当初
有料橋として、大人一銭、人力車二銭であったため別名「一銭
橋」と呼ばれていました。
いくたびかの洪水で流失を繰り返した木造の両国橋は、昭和
23年に永久橋として架け替えられました。
昭和28年堤防改修の際、橋梁の改築が行われ、現在の両国橋と
なりました。
|
| 小林三角和久 |
 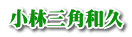 |
小瀬川は洪水のたびたび起こるごとに川の流れを変えた。
このため、洪水から村を守ため、「福島堤防」と呼ばれる
まき石護岸や「小林三角和久」と呼ばれる石組み堤防を築いた。
三角の出っ張りが、水流の勢いを落とす役目をする。
下流の護岸との組合せで、町を守った。
【西国街道を行くより引用】
|
| ごじんじ |
 |
|
大名行列が渡る時に殿様のかごを置く石が再現してあります。
|
| 渡し場のまき石(福島堤防) |
 |
|
古代から数限りない人々がこの渡し場を利用した。昭和56年
12月に大竹市教育委員会の発掘調査で雁木が見つかり、当時を
今に伝えている。また江戸時代初頭につくられた強固な「繢石」
(まきいし)は、度重なる洪水に耐え中津原を守り、昭和58年11
月に大竹市文化財に指定されました。
「繢石」は、「福島堤防」と語り継がれていますが、はっきり
した築調年代はわかっていません。
|
| 木野の渡し場跡 |
 |
|
安芸浅野藩と、周防毛利藩の国境の川、小瀬川がある。西国
街道の渡し場としては、まき石護岸の西側に舟着きスロープが
残っている。
渡し賃は、武士が無料、一般の人は、江戸時代初期でこめ一
合が徴収されていた。中期には、二文、牛馬は四文であった。
渡し場は、舟渡しで川幅約22m、水深1.4m 徒歩渡しで川幅
約22m、水深0.70m程度であった。舟渡しは木野、小瀬村から出さ
れた「渡し守」が二人一組で昼夜交代して行い、その費用は芸防両国
で負担した。
【西国街道を行くより引用】
|
| 木野の本陣開かずの門 |
 |
|
本陣は、集落の北の山沿いにある。街の中心から門が正面に見
える。
この門は、開かずの門と言われ、いつもは閉まっているが、参
勤交代の殿様が来た時のみ、この門が開き木野の渡しまで主が迎
えに出る。塀越しに立派な庭が見える。
【西国街道を行くより引用】
|
| 木野の街並み |
 |
|
安芸の国と周防の国の国境の集落、同じ日本でも当時はちゃん
とした国境、通常では行き来はない。国境を流れる川は小瀬川と
いうが、広島藩では木野の集落の名に由来する木野川と呼んでい
る。
宿場町ではないが、雨などにより足止めはあったようだ。木
野の街並みは、全体がこぢんまりとしているが、昔の風情がよ
くまとまって残っている。【西国街道を行くより引用】
|
| 吉田松陰の歌碑
|
 |
安政の大獄で江戸へ護送される途中の松蔭が、安政6年(1859
年)5月28日、国境小瀬川にさしかかって詠んだ「夢路にもか
へらぬ関を打ち越えて今をかぎりと渡る小瀬川」という歌が刻
まれています。
|
| 浅生塚(あそうづか)と芦路塚(あしろづか) |
 |
|
浅生塚は、元文5年(1740)に浅生庵野坡をしのんで建てられ
ました。野坡は芭蕉に学び、蕉門十哲の一人として名を残しま
した。野坡は、その半生を俳諧の旅に過ごし、大竹にも十数度
滞在しています。その都度俳諧の会を開き、同好の人々「竹
里連中」の指導をしました。
昨飽庵芦路は、厳島の人でしたが、結婚後大竹に住んで野坡
の俳風を伝え、安永2年(1773)頃、73才で亡くなりました。
|
|
中 市 堰 |
 |
|
中市堰は弘化3年(1846年)干拓によって田畑が増えたのを機に
農業用水を引くために作られました。
昭和26年の災害により昭和27年(1952年)に、木製の井堰から
鋼製転倒ゲート(70連)に改築され、現在の中市堰は、平成6年
(1994年)に完成しました。
ゲート数は3門ありその両側には魚の通り道が設置してあります。
この堰は塩水がさかのぼるのを防いだり、小瀬川から農業用水を取る
役割をもつ重要な堰です。
|
| 三分一源之丞の碑 (さんぶいちげんのじょうのひ)
|
 |
|
正保元年(1644)に建設された用水路を、天保年間に瀬田口から
五本松まで延長し、開閉式堰堤(中市堰)と、うぐろ樋(瀬田川の
下を潜り用水を送る仕組み)によって小瀬川から直接水を引き、
和木・装束一帯の農地に潤いを与えた三分一源之丞(天保11年
1840没)父子の顕彰碑です。
源之丞はその完成を看ることなく亡くなりましたが、その志は
嫡子権四郎によって受け継がれ、見事に完成されました。
【和木町HPより引用】
|
| 願掛地蔵 (がんかけじぞう) |
 |
|
その昔、八幡山の崖下は深い淵で、そこに毎晩のように得体の
知れない怪物が現れるというので、日が暮れると怖がって誰一人
通る者がいなくなりました。
そこで、道辺に地蔵菩薩をお祀りしたところ、それから怪物が
出なくなったのでお地蔵様への信仰が高まり、諸事の願掛けが行
われるようになったと伝えられています。
【和木町HPより引用】
|
| 竹原七郎平渡渉地点
|
 |
|
慶応2年6月14日、小瀬川の朝霧を破る銃火砲声は、これぞ
幕府の第二次長州征伐(四境の役)の芸州口戦争の発端であり、同
時にそれは明治維新の黎明をつげる時代の響音でもありました。
この緒戦において幕府の先鋒彦根藩士竹原七朗平とその従者は
先陣を切って小瀬川渡河中、長州軍の銃撃に遭い、壮烈な戦死を
遂げました。
|
| 長州の役戦跡 (大竹口) |
 |
|
慶応2年(1866)5月28日長州藩応戦を布告。幕府の先陣 井伊
・榊原軍が大竹口に軍を進め、木野川を隔てて毛利・吉川軍と相
対した。
6月14日未明、戦いの火蓋は切られ、大竹口で激戦の末、幕
府軍が敗走した。死傷者多数、兵火により家財を失う者は9千人
にのぼった。
|
| 旧大和橋 |
 |
|
大和橋の歴史は古く、江戸時代末期には、現在の位置近くに
土橋があったという記録があります。
幕末以降の大和橋は明治13年の架橋が初代で、その後洪水
などによる流失と修繕を繰り返してきた。二代目は、大正15
年に架けられ、昭和26年ルース台風により中央径間が流失し
ましたが、昭和28年に修復されました。
大和橋は、栄橋が昭和17年に完成するまで、和木・大竹を
結ぶ唯一の橋として、重要な役割を果たしてきましたが、老朽
化が進み平成9年に現在の橋に架け替えられました。
|
| 米元広右衛門の碑 (よねもとひろえもんのひ) |
 |
|
昭和33年(1958年)生産が完全に中止されるまで、和木は海苔
の養殖の大変盛んなところでした。その海苔養殖を和木で初め
て成功させたのが米元広右衛門です。
米元広右衛門(文政6年~明治22年)は、若くして殖産に志
し、織工、製紙、養蚕など多くの事業を手がけましたが、こと
ごとく失敗しました。しかし挫折することなく、晩年小瀬川河
口に海苔の養殖を思いつき、ひたすら研究を続け試行錯誤を重
ねた末、明治21年ついに成功を収めました。
以来、農家では海苔の製造を副業とし、家計を潤しました。 【和木町HPより引用】
|
| 三秀神社遺跡 (みつぼしじんじゃいせき) |
 |
|
200年にわたる吉川、浅野両藩の国境争いの中で、宝暦2年(1752)10月、小瀬川口の与三野地で起こった騒動は乱闘の末、
双方に多数の死傷者を出す惨事となりました。
それから50年後の享和2年、両藩は和解し国境が確定しまし
た。この時、吉川藩主は祠を建て、犠牲となった野脇新六、坂戸
源右衛門、兒玉良兵衛の3人を神に祀りました。
【和木町HPより引用】
|
| 鼻繰南蛮樋 (はなぐりなんばんひ) |
 |
|
この樋門は元禄3年(1690)3月、この地(中新開、面積26町
9畝23歩 約26㌶)の築造時に潮止めのため設けられたもの
です。
当時この樋門の内側に鷹匠の池と言われる沼があり、芦蒲が茂
って鷺鴨が多く生息し鷹猟が行われていたと伝えられています。
|
| 享和開作の碑 |
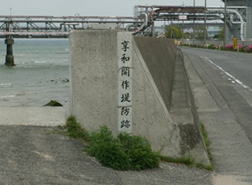 |
|
享和開は享和3年(1803)芸防国境和談成立によって領境が確定
し、小瀬川が一条筋となった際はじめて藩営で干拓されたもので
堤防を築き潮止めをし内側の陸化に成功したものである。(干拓
面積32町余)
|
| 小島新開の常夜燈 |
 |
|
小島新開は天保3年(1832)に造られました。この石灯籠は天保
6年(1835)大阪の商人や大竹の有志により、航海の安全を祈って
住吉神社に奉納されたものです。高さが約 4.8㍍ある常夜燈です。 当時、大竹では和紙が盛んに作られていましたが、この常夜燈
は、河口をとおり木野川を上り下りして商いをした船の燈台の
役目をはたしました。
|