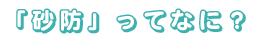
 「砂防」の語源 「砂防」の語源 |
||||||
| 「砂防(さぼう)」という言葉は古く、江戸時代には「砂防工事」を「土砂溢漏防止(どしゃいつろうぼうし)」と言っていましたが、これを簡単に表現して「砂防」としていたようです。 土砂災害防止工事は、明治以前にも全国各地で行われていましたが、広島県東部では、江戸時代に普請(ふしん)※した堰堤(えんてい)が現存し立派に機能しています。写真は、「堂々川(どうどうがわ)第6番砂留(すなどめ)」(福山市神辺町西中条 堂々川)です。この砂留は、土砂の流出による下流の被害を防ぐ目的で普請されたものです。 ※普請:土木工事のこと。 |
||||||
|
||||||
 世界に広がる「砂防」 世界に広がる「砂防」 |
||||||
| 外国で砂防のことをSABOといいます。日本語がそのまま世界の共通語になっているのです。日本の砂防技術がすぐれていること、日本が海外のいろいろな国で砂防の技術指導をしていること、砂防にあたる適当なことばが外国語にはないこと、などが理由で、1950年ころから、SABOということばが使われるようになりました。 | ||||||
 身近でできる砂防 身近でできる砂防 |
||||||
| 「土砂災害」への予防は、日々の観察から始まります。詳しくは、『「土砂災害」を防ぐために』の項目をごらんください。 |
