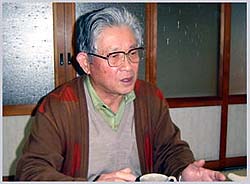6.29災害の様子 6.29災害の様子 |
| 土石流の被害が起きた安佐北区勝木地区の自主防災組織「亀山西地区まちづくり協議会会長」綿崎英之氏に6.29災害の当日の様子などを貴重な体験をお聞きしました。 |
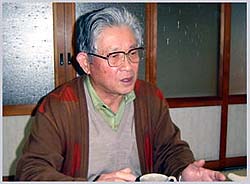

綿崎英之氏/亀山西地区まちづくり協議会会長 |
平成11年6月29日、午後12時を過ぎ、安佐北区勝木地区では、バケツをひっくり返したような雨が続いていました。
当日、家の中で過ごしていましたが、あまりにも激しい雨のため、家の周りの水路や倉庫などを点検するために外に出かけると、家の周りの道路や田畑が、水で埋め尽くされていました。
また、外は激しい雨のため視界が悪く、遠くの様子ははっきり見えない状況でした。
なおも、激しく雨が降り続いたため、午後3時あたりに地域の状況を把握するよう、子供の頃から度々、氾濫した大毛寺川へ行くと、すでに川が氾濫しており、氾濫した川の水位は、腰の辺りまで、上がっていました。 |
| 氾濫した川のあたりでは、独り暮らしの老人やその他の方々が取り残され、孤立状態にありました。そのため、自治会やご近所の方々と話し合い、避難させるために消防団の力を借り、救出をしました。 |
|
 |
 

6月29日の安佐北区亀山地区(撮影:綿崎氏) |
 |
| 避難活動を行なっているところ、大毛寺川上流の方を見ると、すごい土煙が上がっており、周辺の被害状況を把握しながら、土煙が上がっていた場所へ到着すると、既に家は土石流によって押し流されていました。2箇所同時に土石流が発生したため、かなりの力によって、家が破壊されたのだと思います。 |
 |
| 捜索には、消防署、広島県警があたり、約200人程度を投じた捜索活動が行なわれました。現場では、自治会として、何が出来るかを消防署及び広島県警と話し合いの結果、捜索活動を続けている方々への食事の配給を行ないました。約4日間にわたる捜索活動が続けられましたが、残念ながら、お年寄りや幼児など含む5名の尊い命が失うこととなりました。 |
| 捜索活動の終了後、自治会では、土砂や流木、ボロボロになった家具などの撤去作業、他の被害の復旧作業など200名を動因して作業に当たりました。 |
| 復旧作業にあたり、様々な場所では、流木が家を直撃して破壊されていたり、道路には約1m50cmぐらいの大きな岩が20個程度転がっていました。もし、大きな岩が住宅を直撃していれば、もっと大きな被害になったのではと思います。 |
| 災害後は、綿崎氏を中心とした自治会による自主防災活動を組織化し、広島市が作成した災害マニュアルを亀山地区にあった災害マニュアルとなるよう、広島市の指導を仰ぎながら修正を加え、避難経路や避難場所の見直しを行ないました。また、無線連絡体制を構築し、大毛寺川が氾濫しそうな場合などの時には広島市への連絡をするとともに、避難活動を行なえる体制づくりを行なっています。 |
| やはり、大きな被害に会わないためにも、役所の指示だけを待つのでは無く、自分たちの命は自分が守るという意識を持って、自ら情報収集を行ったり、適切な知識を持つための努力、地域のネットワークづくりが大切であると思います。 |
 |
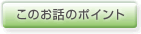 |
| |  | | |
|  |  |  | |
 |  |
・自分たちの命は自分が守るという意識を持つこと
・自ら雨量情報など情報収集に努め、災害に対する適切な知識をもつこと
|
 |
 |
|  |  |  | |
| |  | | |
|
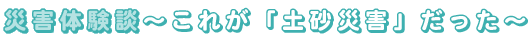
 6.29災害の様子
6.29災害の様子