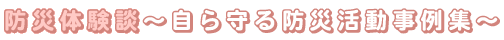
 災害概要 災害概要 |
| 昭和63年 7月豪雨 (最大時間雨量56.0mm,死者14人) |
 気象概況 気象概況 |
|
7月20日9時、梅雨前線上の低気圧が日本海南部をゆっくり東へすすみ、20日21時には能登半島付近に進んだ。この低気圧から朝鮮半島中部に延びる前線は、オホーツク高気圧の強まりに伴い15時には山陰沖までゆっくり南下し、この前線沿いに暖湿流が入り前線活動が活発となり、大雨の降りやすい状態となった。 前線はその後もゆっくり南下を続け、気象衛星(ひまわり)の画像によると、山陰沖で急激に発達した雲は、山陰西部から広島県の北西部に南東進した。 この強い雨雲の発達した状態は、22時頃から〜6時間持続し、県北西部に局地的な大雨を降らせた後、21日9時には瀬戸内まで南下し、県内の雨は止んだ。 |
 被害状況 被害状況 |
| 昭和63年7月豪雨の特徴は、集中豪雨による土石流災害である。 被災地は、広島県北西部の主に加計町、戸河内町、筒賀村の一部に集中した。 この地域一帯の地質は、黒粗粒雲母花崗岩を基盤岩としており、これが風化してできたいわゆる「マサ土」である。 水を通しやすくもろいマサ土になりきれない岩が点々と残っており、短時間の豪雨で谷を下る水は、渓床に堆積した土砂とともに渓岸をえぐり、立木をなぎ倒し、砂防ダムを乗り越えて山裾の集落を襲った。計10ヶ所の渓流で土石流が発生し、民家は、流出・埋没し、また死者14人、負傷者11人という大きな被害を被った。 さらに農林業、土木、鉄道等にも大きな被害を受けた。 昭和63年7月豪雨で土石流が発生した渓流は、200年前の寛政8年(1796年)に土砂災害が発生した渓流とほとんど同じであった。 |
| →昭和64年7月豪雨の災害体験談 【PDF形式 642KB】 |
| →災害体験談一覧へ戻る |