| <<前のページ |
|
 |
| ウナギ |
| ウナギ目 ウナギ科 |
| 日本では北海道以南に分布する。河川の中流・下流、河口や湖沼に生息する。海にもいる。ウナギの幼生期はレプトケファルス(葉形幼生)と呼ばれる、成魚とはまったく異なる体で、水中を浮遊する。ダム湖では流れが非常にゆるやかな場所に生息する。 |
|
|
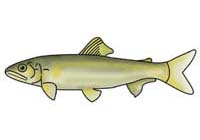 |
| アユ |
| サケ目 アユ科 |
| 日本では北海道西部以南から九州南部まで分布し、河川の上流・中流、清澄な湖、ダム湖などに棲む。全長10〜30
cm。春から秋には川の中流で生活し、夏の終わりから秋にかけて川の中流部で産卵する。ふ化した仔魚は秋に海に降り、
春に川をさかのぼる。 |
|
|
 |
| オヤニラミ |
| スズキ目 ケツギョ科 |
| 全長 13 cm。日本では、中国地方や四国北部、九州北部に分布。水の澄んだ流れの緩い小川や溝にすむ。 |
|
|
 |
| ブルーギル |
| スズキ目 サンフィッシュ科 |
| 原産地は北アメリカ中・南部。移植され日本各地の淡水域で爆発的に増えた。在来種の卵や稚魚を食い荒らすため、生態系への影響が懸念されている。体長は25cmほど。ブルーギルは「青い鰓(えら)」という意味。産卵期になると雄は顎に淡青色の帯がでて腹部は鮮やかな橙色になるという婚姻色が出る。ダム湖の湛水部に生息するが、遊漁者等による放流で移入したと考えられる。 |
|
|
 |
| ヌマチチブ |
| スズキ目 ハゼ科 |
| 全長 8 cm.。体は円筒状。日本では、青森県から九州に分布。汽水域を好むが純淡水域でも繁殖できる。土師ダムでは、平瀬の河床の石礫周辺で多く確認されている。環境条件や、その個体の状態により、体色や斑紋の変異が大きく、見分けが難しい。 |
|
|
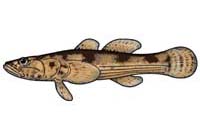 |
| ドンコ |
| スズキ目 ドンコ科 |
| 日本固有種と考えられている。新潟県以西の日本海側、愛知県以西の太平洋海側から四国、九州にかけて分布し、河川よりも、細流や水田などの小水域に生息する。土師ダムでは、湿地付近の細流でみられる。全長25
cm。体はずんぐりしている。 |
|
|
 |
| ヨシノボリ |
| スズキ目 ハゼ科 |
| 日本各地に分布。土師ダムでは、ダム湖に放流したアユの稚魚などに混入して移入したと考えられる。水深が浅く流れの緩やかな平瀬や細流に生息する。全長8cm。 |
|
|
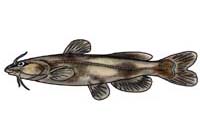 |
| ギギ |
| ナマズ目 ギギ科 |
| 日本固有種で、中部地方以西の本州、四国の吉井川水系、九州北西部に分布する。背びれと胸びれに鋭いとげがあり、このとげには毒があるといわれている。河川の中・下流域、緩流域、湖沼の岩礁、護岸堤の石垣の間などにすむ。全長30cm。ダム湖では、流れが緩やかで、砂泥底の比較的水深の深い場所でみられる。 |
|
|
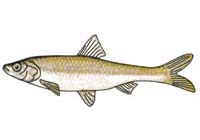 |
| イトモロコ |
| コイ目 コイ科 |
| 土師ダムでは、川岸のヤナギやツルヨシが生育している場所に生息している。 |
|
|
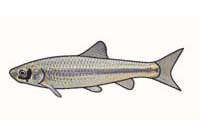 |
| ホンモロコ |
| コイ目 コイ科 |
日本固有種。琵琶湖・淀川水系にのみ分布。他地域での分布は移殖によるもの。全長14cm。タモロコに似るが、それより体が細長く、口が上を向き、口ひげが短い。
土師ダムでは、ダム湛水部などに生息している。
|
|
|
| 2/2 ページ |
 魚 類
魚 類 
 ページの先頭に戻る
ページの先頭に戻る
 魚 類
魚 類 
 ページの先頭に戻る
ページの先頭に戻る