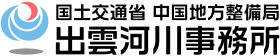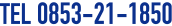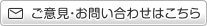第3回
資料
- 資料-1 議事次第・出席者名簿・配席表 (PDFファイル 44.8KB)
- 資料-2 第2回懇談会での意見概要 (PDFファイル 46.2KB)
- 資料-3 斐伊川流域の水辺を考える懇談会 (PDFファイル 69.5KB)
- 資料-4 第3回斐伊川流域の水辺を考える懇談会 資料
- 宍道湖の保全・整備に関するマスタープラン (PDFファイル 1.34MB)
- 平成4年以降の変遷 (PDFファイル 1.08MB)
- 主な景観地 (PDFファイル 1.21MB)
- 鳥類、魚類、水生植物 (PDFファイル 860KB)
要旨
発言要旨
| 出 欠 | 氏 名 |
|---|---|
| ○ | 木幡 修介 氏 |
| 塩飽 浩一郎 氏 | |
| ○ | 田江 泰彦 氏 |
| ○ | 野津 登美子 氏 |
| ○ | 福島 律子 氏 |
| ○ | 藤岡 大拙 氏 |
| 丸 磐根 氏 | |
| ○ | 吉田 薫 氏 |
※五十音順
宍道湖南岸に夢ある水辺ゾーンを
山陰中央新報社相談役 木幡 修介 氏
道湖南岸の国道9号と国道54号が接した付近から宍道湖沿いに延びる堤防上と、干拓地、昭和新田を走る道路は、理想的なジョギングコースでしたが、今はどんどん埋め立てられています。
何かしっかりとした計画に基づいているのでしょうか。
この辺りは、山陰自動車道から降りて来る時に見える景色であり、堤防の法面全体にポピ-などを植えれば、広大でカラフルな楽しいゾ-ンが産まれると思います。宍道湖南岸は整備が遅れていますが、資源がないのではなく、行政も民間も、そして地元にもここに目を向けるという人がいない、もったいないように感じます。
この干拓地を含む宍道湖西岸にはマガンの飛来もあるそうですが、開発が進む中、後で後悔することのないよう夢のある水辺ゾ-ンの形成を図って欲しいものです。
人と宍道湖の接点から、水辺のあり方を探る
島根経済同友会代表幹事 田江 泰彦 氏
懇談会を通じて感じたのは、人それぞれ宍道湖といろいろな形での接点を持っており、その接点が大事だろうということです。子供と一緒に水の中に入って宍道湖を体験し自然を感じる、野鳥を見ながら今の自然の状況を感じる、観光に訪れた人々が宍道湖の景観や夕日をご覧になって生き返ったといってお帰りになる、その様子を見るというふうに、人と宍道湖がどういう風に関わっているのかといった観点です。宍道湖のあり方を考える上で大事なのは、現在、ここにすむ人や周辺地域の人々、また観光などで訪れる人々が、宍道湖との接点の中でどういうことを感じ、どうあって欲しいかと願っているかということだと思います。それはその時点、その場のことだと思いますから、はじめからゾーンにくくるというのではなく、個々の場所を議論し、その上である程度全体のイメージをくくっていくということでもよいのではないかと思います。
人と自然の触れあいは、自然へのちょっとした配慮から
ホシザキグリーン財団企画交流課長 野津 登美子 氏
ラムサール条約に登録されても、昭和干拓のように埋め立てられて、鳥たちの生活に必要なねぐら・えさ場・休息場といった条件が確保されないと、野鳥が寄りつかなくなってしまいます。例えばマガンでは、宍道湖をねぐら、斐伊川河口の砂州を休息場、そのまわりに広がる田んぼをえさ場というふうに、コンパクトにセットされています。しかし、最近田植えが遅くなっており、白鳥は早場米地帯である浜佐陀の方へどんどんといってしまっています。こういうちょっとしたことが野生の動物には影響してしまうので、人間が何かをするときに少し配慮する仕組みがあると、西岸域の人と自然がふれあう水辺は本当に保たれていくと思います。
また、宍道湖の水のある風景はすごくいやされますし、風景は大事にして欲しいなと思います。風景を売り物にするのであれば、背景にもこだわって欲しいと思います。
現実感のあるゾーン区分を
松江市教育委員会教育長 福島 律子 氏
水辺のあり方(案)について、その土地との土地の特徴をつかんでイメージを作ろうとした努力は大変にうかがえると思います。しかし、南岸に住み、毎日その水辺を見て通勤している者として、少ししっくりこないという感じを抱きました。そうあるべき、という考え方かも知れませんし、もう少し実際の感覚に合ったものがないかなと思います。
また、水辺のあり方を表現する言葉そのものについても、どうかなと思う表現もあり、一考の余地があると思います。
その他、水辺のあり方を考えるとき、全体としては、産業との関わりのようなことも考える必要があるのではないでしょうか。
目標に向かって努力を
島根県立島根女子短期大学名誉教授 藤岡 大拙 氏=座長
水辺のあり方については、表現をもう少し整理したら、それを努力目標として、取り組んでいくというふうなことになれば、まことにいいなという風に思います。反対に、目標と実態がひどく違うということになると困りますので、目標に向かって努力をしていく必要があります。
大橋川の矢田の渡しの周辺は風土記で、あまりにも魚が多くて、はねて土地に上がり、干からびたものを鳥が食べるというような、極めて鮮明な情景が出てくる場所であり、いにしえの流れを感じる水辺はいい言葉だと思います。
美しい宍道湖を守っていこう、そして安らぎのもとにしようという思いは皆さん一緒ですので、その想いが実現できるような水辺のあり方を提言したいと思います。
心やすらぐいやしの湖
風景研究室代表 吉田 薫 氏
宍道湖というのはどういうイメージの湖なのかと考えたとき、懇談会での意見やアンケート調査等からみて、「いやし」という言葉が重要な要素ではないかと思います。大気が水分をたくさん含んでやわらかく見える、あるいは高い山がなく平遠な景色であることで、心が安らぎいやされるのではないでしょうか。「いやし」を中心に据えて考えると、ジェットスキーのような騒々しい水上活動ではなく、静かな楽しみ方の方が宍道湖にはふさわしいように思われます。
北岸と南岸については明らかに雰囲気の違いがあります。そして、その中にスポット的ににぎわった場所や少し性格の異なる場所があるといった感じで、それぞれにおける東と西の違いはあまりないというのが実感です。夕日の写真を撮る場所としては、嫁ヶ島の前が圧倒的にいいわけですが、北岸の松江市役所の前などでも夕日を眺めている人がいます。今回の水辺のあり方(案)の ゾーニングは、このような実態と少し違う気がします。