 |
 |
 |
 |
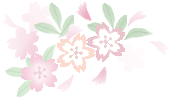 |
土師ダム貯水池である『八千代湖』湖畔は、春には6000本の桜が咲き乱れ、県内有数の桜の名所となっています。 |
| 花の季節は見事な景観をなし、個々の木を見ると病虫害に侵されているものが多く、このままでは名所の座を降りなければならないほどになっています。
|
| 近年、多くの桜は老齢化が進み、てんぐ巣病などにかかった桜や生育不良の桜も多く場所によれば著しく景観を損ねています。 |
| このまま、放っておくと現在健全な桜にも病気が広がり、土師ダムの桜が枯れてしまう可能性があります。 |
|
適切な管理と更新が緊急の課題となっており、今後、桜の名所としての八千代湖を守っていくために、関係地域の住民の方との協働により必要な手入れ(間伐等)を行っていきます。 |
| 皆様のご理解とご協力をお願い致します。 |
 |
|
|
|
 |
 |
八千代湖のサクラって?
|
|
 |
 |
 |
| 八千代湖のサクラは大部分が「ソメイヨシノ」と呼ばれる種類です。 |
|
このサクラは、江戸時代中期〜末期に園芸種として生まれ、葉より先に花が咲き開花が好まれ、明治から戦後にかけて日本中に植えられ、全国に爆発的な勢いで植樹されました。 |
 |
 |
| ソメイヨシノ |
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
何が問題なの?
|
|
 |
 |
 |
ソメイヨシノは、サクラ全般の共通欠点として、大気汚染などの環境悪化に弱いことや、病害虫の被害を受けやすいことに加えて、特に免疫力が弱く、てんぐ巣病やきのこの寄生などの菌の繁殖による病気にかかりやすい傾向があります。
|
 |
サクラの病気は
こちら
|
 |
 |
 |
 |
| てんぐ巣病で枯れが進行しているサクラ |
きのこが着生したサクラ |
|
|
 |
 |
ソメイヨシノの自然な成長には、一般的に10〜12mの間隔で植樹することが良いとされていますが、土師ダム周辺のサクラは近い箇所では2m間隔で植えられている所もあり、木の生育につれてお互いに障害となり、生育を妨げている木が多くみられます。これが、結果的に細く高い木を生むことになり、木自体の耐性も弱まったことに加え、枝の接触による病害虫の感染が広がる原因となったと考えられます。
|
 |
 |
 |
 |
| 隣の木と枝が絡まるサクラと昼間も暗いサイクリングロ−ド |
|
|
|
|
|
 |
 |
どうすればいいの?
|
|
 |
 |
 |
関係地域の住民の方との協働により、病弱化しているサクラに対して、元気を取り戻すために手入れを行います。サクラの元気回復とともに、付帯作業として灌木や下草の除去を行うことで、害虫の発生やゴミの不法投棄も少なくなり、サイクリングロ−ド周辺の環境改善にもつながると思いますので、皆様のご協力を御願いします。
|
|
|
 |
 |
 |
木の間隔を広くします
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
サクラ同士の樹間を広げるために、間隔の狭い部分の木を伐採(間引き)します。 |
 |
 |
病害虫の被害を受けた枝が接触して被害が広がらないように、枝打ち(枝の剪定・削除)をします。 |
|
 |
 |
 |
水はけの良い肥沃な土壌の復活
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
水はけの不良箇所を改良し、過湿状態を改善します。根元に水が溜まりやすい状況を避けるようにします。 |
 |
堆肥を施して土に栄養を与え、土壌の回復を図ります。 |
|
 |
|
|
|
 |
 |
桜守プロジェクトって?
|
|
 |
 |
 |
土師ダム水源地域ビジョンの一環で、八千代湖の桜を後世に伝え残していくため、行政のみならず桜を愛し楽しむ住民を「桜守」として登録し、住民との交流・協働の中で、桜の維持・保育を楽しみながら行っていくものです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |





