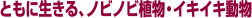 |
灰塚に暮らす人々の生活を文えてきた田総川と上下川は、流紋岩や安山岩の断層に沿って流れています。この流れが削った土砂が積もって平地をつくり、そこに耕地を拓いて人々が住み着きました。
この周辺を歩いているとたくさんの友達に出会います。それらの友達と私たちは昔から、仲良くしたり、助けあったり、ときには戦ったりしてきました。そう、友達とは都会の人々が求めて止まない豊かな自然そのものです。
それではここで、灰塚の植物を紹介しましょう。コナラにアベマキ、シラカシ、アラカシ。ツルヨシ、マコモ、ネコヤナギ。カエデ、ケヤキに…。春の訪れを告げるもの、秋の山に彩りを添えるもの、森の動物たちの餌を提供してくれるもの、そんな木々がいっぱいです。人工林ではヒノキがまっすぐ背を伸ばし、もっと上を目指しています。
今では見ることが少なくなったセツブンソウやカタクリも、ここではそっと可憐な花を咲かせています。きれいだからって摘んで帰ってはいけません。山で見るのが一番です。
もちろん動物もいっぱいです。天然記念物のオオサンショウウオに、県下でも珍しいブチサンショウウオ、オヤニラミ、アカザ、カネヒラ、タカハヤ、美声を響かす力ジ力もいます。哺乳類ではアナグマやイノシシ、キツネなどが元気に暮らしています。夜、道路を走つていると、タヌキがひょっこり現われて驚かされることもあります。
|
|
セツブンソウ
(キンポウゲ科)
セツブンソウは日本固有の種で、節分(2月上旬)のころに花を咲かせます。関東以西に自生しますが、環境の変化によって次第に減少し、いまでは希少植物となっています。北向きの山すそに群生していますが、夏になると土の中に影を潜めて見ることができません。ちなみに総領町は日本最大の群生地です。
|
ナラガシワ
(県天然記念物)
三良坂町灰塚のナラガシワは樹高16m、根間り4.2m、胸高岡岡約3.5mもある巨木で、しかもかなりの古木でもあります。ナラガシワは日本では近畿、中国、九州に多く繁殖していましたが、現在では天然樹はほとんど見られず、このような巨木、老木は極めてまれな存在です。
|
|