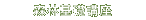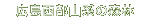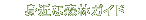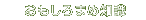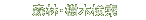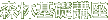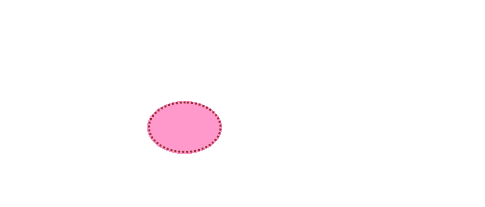身近な森林からわかること
今までの内容を、おさらいしてみましょう。
広島西部山系によく見られる森林を対象に、これらを整理すると、およそ次のとおり関連づけることができます。※表中の森林名をクリックしてください。

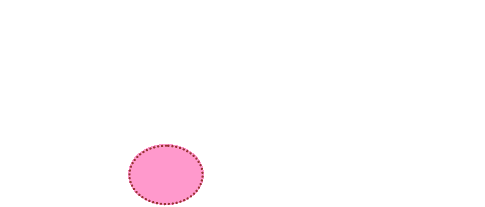

- 常緑樹林
- 鎮守の森として、地域の人々に大切に守られてきた林です。 この林からは、次のようなことがわかります。
- 人間が森を切り開く前には、このような林が、平野部一帯に広がっていたこと。
- 昔、広がっていた時の、植物の種類や林の様子。
- 現在、身近な山に広がるアカマツ林や落葉樹林の将来の姿。
- 大切に守り続ければ、将来も常緑樹林のまま維持されること。


- 奥深い山の落葉樹林
- 山の奥深くにある、大木を交えた落葉樹林です。この林からは、次のようなことがわかります。
- ふもとの薪炭林(しんたんりん)のような、定期的な伐採は行われてこなかったこと。
- 昔、涼しい気候の山域に広がっていた落葉樹林の様子や、植物の種類。
- 伐採されなければ、将来も、ほぼ同じ姿の林が見られること。
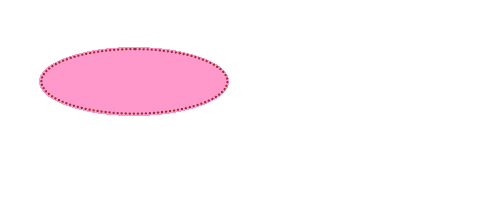

- アカマツ林
- 本来なら、常緑樹林が広がっているはずの所です。 そこに、アカマツ林(針葉樹林)広がっていることから、次のことがわかります。
- その昔、人間が燃料として木を切ってきたという歴史をもつこと・乾燥したやせた土地であること。
- 将来は、林内に生育している常緑樹の林へと遷移すること。
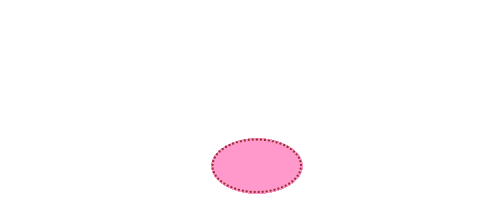

- ふもとの落葉樹林
- 本来なら、常緑樹林が広がっているはずの所です。 そこに、落葉樹林が広がっていることから、次のことがわかります。

- その昔、人間が燃料として炭やまきを採るために利用してきた林であること。
- 高木の株立ちも、繰り返し伐採されてきた歴史を語っていること。


- 明るい場所の低木林
- 少し前に、伐採や土砂崩れなどの影響を受けたことを示す林です。この林からは、次のことがわかります。
- このまま放っておくと、遷移が進んで、背の高い森林へと変化すること。
- 再び土砂が流失したり、伐採が行われると、また、裸地や草むらからの遷移が始まること。
- このような明るいやぶのような場所には、アゲハチョウの仲間のエサとなる樹木が多く、昆虫採集のポイントとなること。
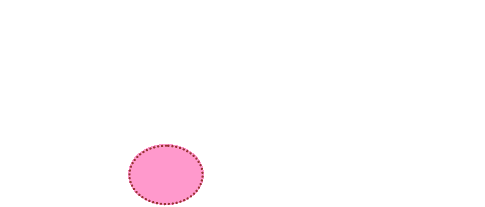

- 常緑樹林
- 鎮守の森として、地域の人々に大切に守られてきた林です。 この林からは、次のようなことがわかります。
- 人間が森を切り開く前には、このような林が、平野部一帯に広がっていたこと。
- 昔、広がっていた時の、植物の種類や林の様子。
- 現在、身近な山に広がるアカマツ林や落葉樹林の将来の姿。
- 大切に守り続ければ、将来も常緑樹林のまま維持されること。


- 奥深い山の落葉樹林
- 山の奥深くにある、大木を交えた落葉樹林です。この林からは、次のようなことがわかります。
- ふもとの薪炭林のような、定期的な伐採は行われてこなかったこと。
- 昔、涼しい気候の山域に広がっていた落葉樹林の様子や、植物の種類。
- 伐採されなければ、将来も、ほぼ同じ姿の林が見られること。
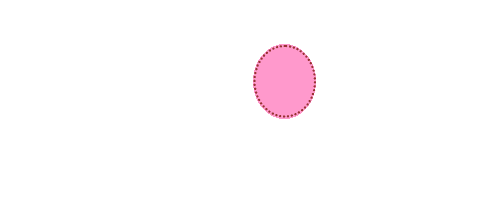

- 岩場のアカマツ林
- 低木がまだらに生えている、岩場の林です。この林からは、次のことがわかります。
- 植物にとって、「きびしい場所」であること。
- 遷移はなかなか進まず、遠い将来にも、この特殊な景観が見られること。
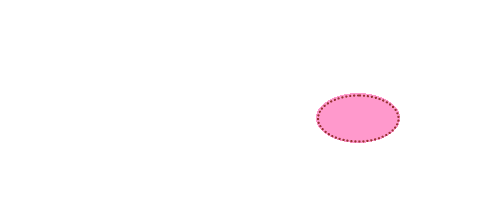

- 渓流沿いの落葉樹林
- 渓流に沿って見られる落葉樹林です。
本来なら、常緑樹林が広がっているはずの所にあるこの林からは、次のことがわかります。- 土砂の移動が多く、時に、土ごと林が流れ去ってしまう立地を示していること。
- 伐採されなければ、流失と再生を繰り返しながら、将来も、渓流沿いを彩ること。


- 明るい場所の低木林
- 少し前に、伐採や土砂崩れなどの影響を受けたことを示す林です。この林からは、次のことがわかります。
- このまま放っておくと、遷移が進んで、背の高い森林へと変化すること。
- 再び土砂が流失したり、伐採が行われると、また、裸地や草むらからの遷移が始まること。
- このような明るいやぶのような場所には、アゲハチョウの仲間のエサとなる樹木が多く、昆虫採集のポイントとなること。
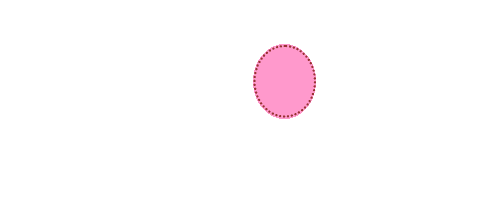

- 岩場のアカマツ林
- 低木がまだらに生えている、岩場の林です。この林からは、次のことがわかります。
- 植物にとって、「きびしい場所」であること。
- 遷移はなかなか進まず、遠い将来にも、この特殊な景観が見られること。
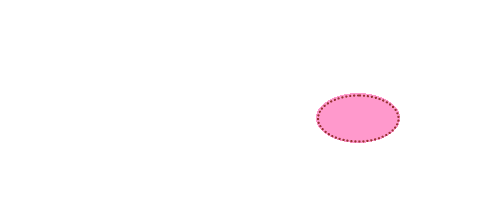

- 渓流沿いの落葉樹林
- 渓流に沿って見られる落葉樹林です。
本来なら、常緑樹林が広がっているはずの所にあるこの林からは、次のことがわかります。- 土砂の移動が多く、時に、土ごと林が流れ去ってしまう立地を示していること。
- 伐採されなれば、流失と再生を繰り返しながら、将来も、渓流沿いを彩ること。