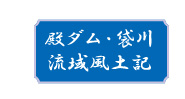

民話・伝説 2 |
 |
 |
 |
 |
11、冥府への入り口伝説<十王峠> |
|
| 十王とはこの世でおかした罪を裁く、秦広王(不動明王)・初江王(釈迦如来)・宗帝王(文殊菩薩)・五官王(普賢菩薩)・閻魔王(地蔵菩薩)・変成王(弥勒菩薩)・泰山王(薬師如来)・平等王(観音菩薩)・都市王(勢至菩薩)・五道転輪王(阿弥陀如来)の十人の王たちのことであり、この峠があの世の入口と信じられていました。 |
|
11、ケイ東塚の哀話<十王峠> |
|
| 十王峠を越えて銀山村へ向かう道沿いに酒屋がありましたが、ある冬、雪が家を押しつぶして一家の人々は残らず圧死してしまいました。その主人に“ケイ東”と法名がつけられたので、弔われたこの塚を「ケイ東塚」と呼びました。 |
|
11、太閤の一口水<十王峠> |
|
| 銀山村より登って十王峠の峰の右、道ばたの平地に清水が湧き出ています。羽柴秀吉が城攻めのためにこの峠を越そうとした際、炎暑で武将達が喉を乾かしていたので、秀吉が鎗の石突きを地に突き通したところ、そこから水が湧き出しました。その後、銀山が繁昌の時にここに鉛座を建てたので、鉛座清水ともいわれました。 |
|
13、舟山伝説<舟山> |
|
| あるとき大津波が起こり、賀露の浜から鳥取の町を一飲みにして国府の里におし寄せました。一ノ宮の社の庭まで水が届き、岡益の奥では溢れた水が私都方面に流れ出し、松尾の土堂薬師のお堂の上にまで水がきました。このことから岡益の奥を「水越」というようになり、一ノ宮の広庭と水越と薬師堂の高さが同じだと語られるようになりました。津波が引いたあと、新井村の氏神様の右側の山の中腹に津波で打ち上げられた一艘の小舟が止まっていて、のちにこの地は「舟山」と名づけられました。 |
|
14、安徳天皇伝説<御陵山・岡益の石堂> |
|
| 壇ノ浦から岡益の里へ落ち延びできた安徳天皇は、文治3年(1187)8月13日に御年10歳にして崩御されました。お仕えしていた人々は悲しみながら冬頃から翌年秋までかかって縦一丈六尺、六間四面の石堂を建立し、その中心に石棺を置いて御骨を納めました。ここを西の「帝石堂」と名づけて安徳天皇のご霊場とし、石堂のある山を御陵山と呼びました。 |
|
15、三種の神器の伝説<酒賀神社> |
|
| 安徳天皇と落ち延びてきた二位の尼が三種の神器をこの宮に託されましたが、江戸時代に雲州の神官門脇好井が出雲へ持ち帰り、代わりに神器を模した三幅を寄進しました。 |
|
15、安徳天皇伝説<崩御ヶ平> |
|
| 安徳天皇一行が因幡の国に落ち延びてきてからのち、瓢箪山に暮らして荒舟の山奥の見晴らしのよいところへお連れしたところ、急に気分が悪くなって崩御されたことから、この場所は崩御ヶ平と呼ばれるようになりました。 |
|
16、二位の尼の伝説<新井の石舟古墳> |
|
| 安徳天皇の祖母、二位の尼が亡くなり、泉が谷の石舟に葬られました。二位の尼の墓所があるところからこの地を“二位”と読んでいましたが、後に“新井”と改められました。 |
|
17、梶原橋伝説<谷> |
|
| 源氏の梶原平三景時が平家一門の滅亡をいち早く調査し源頼朝に報告するため、壇ノ浦から石見・出雲・伯耆と浦伝いに谷村までやってきました。しかし、風雨が激しく袋川の水が溢れ、横切ることができませんでした。そこで景時は近在の村人に木材を出させて船筏に組み、やっとのことで人馬とも渡ることができました。その後、この場所にできた橋を梶原橋といいました。 |
|
18、谷の観音様の伝説 <峰の観音> |
|
| 和泉式部の誕生 御慈悲の巨石 海の守り 大蛇の慈悲心 盗賊のざんげ 情けの道連れ 観音のみちびき |
|
19、キツネのあだうち伝説<神垣> |
|
| 神垣村に源兵衛という百姓が住んでいました。畑に行ってみると、キツネが一匹気持ちよさそうに昼寝をしていたので、小石を投げて脅かしました。家に帰ると裏口の向こうでキツネが遊んでおり、葉っぱに水溜まりのアオミドロをかけると大ふろしきになり、小さな竹は日笠に、キツネは美しい娘に化けました。その夜、訪ねてきた自分の娘を化けたキツネと勘違いしてひどい目にあわせてしまい、自分がキツネにだまされていたことをようやく悟りました。 |
|
20、羽柴秀吉の大笑い伝説<笑い道と加藤橋> |
|
| 柴秀吉が城攻めを行っていた折、私都の市場城を攻め落とすため三代寺より峰寺へ山越えをする途中で一服し、市場城を眺めながら余裕の大笑いをしたといわれ、それ以来この道は「笑い道」と呼ばれています。そして、峰寺の前の小川に加藤清正に命じて土橋を架けさせたため、この橋は加藤橋と呼ばれています。また、この道は後醍醐天皇が隠岐島から京都へお帰りになる時に通った道だともいわれています。 |
|