斐伊川水系
21世紀に向けて展開する現代のくにづくり
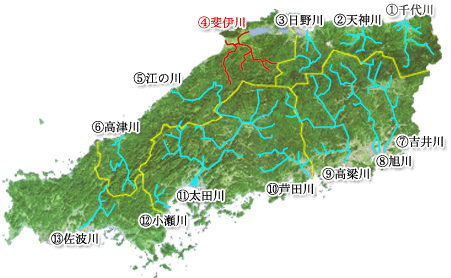
| ①千代川 | ②天神川 | ③日野川 | ④斐伊川 |
| ⑤江の川 | ⑥高津川 | ⑦吉井川 | ⑧旭川 |
| ⑨高梁川 | ⑩芦田川 | ⑪太田川 | ⑫小瀬川 |
| ⑬佐波川 |
流域の地勢、気候上の特色
斐伊川は,その源を島根県仁多郡奥出雲町の船通山に発し,多くの支川を合わせながら北流し,出雲市大津町上来原で斐伊川放水路を通じて神戸川へ洪水を分派した後,出雲平野を東へ貫流し,宍道湖,大橋川,中海境水道を経て日本海に注ぐ,幹川流路延長153km,流域面積2,540平方kmの一級河川です。
神戸川は,その源を島根県飯石郡飯南町の女亀山に発し,支川を合わせながら北に流下し,出雲市上塩冶町半分で斐伊川放水路と合流して,出雲市を貫流した後,日本海(大社湾)に注ぐ流路延長82.4kmの河川で,斐伊川放水路事業による斐伊川との連結により,平成18年8月1日に二級河川から一級河川に指定され、斐伊川水系に編入されています。
斐伊川流域は古代より「出雲國」と呼ばれ、当時政治的にも文化的にも日本の拠点の一つであったと考えられています。奈良時代に編纂された「古事記」、「日本書紀」、「出雲國風土記」でも,出雲地方を舞台にした神話等が数多く記録されており,「神話の国」と呼ぶにふさわしい歴史と文化に彩られた地域です。
流域の気候は,年間を通じて曇天の日が多く,年間降水量は,平地部で1,800~2,000mm,山間部で2,000~2,200mm程度と梅雨期を中心に多くなっています。
斐伊川の下流部では,「鉄穴流し」と呼ばれた山砂からの砂鉄採取に伴う廃砂により,多量に流入した土砂で,堤防より居住地側の地盤高に対して河床が3~4m程度高い天井川が形成されています。また,宍道湖および中海は,日本海との水位差が数cm~10cmと小さいうえ,両湖を結ぶ大橋川の川幅が狭いため,洪水時には水はけが悪く,洪水に対して脆弱な地形となっています。
斐伊川下流部の出雲平野は,古くから洪水の氾濫に悩まされながらも,出雲地方の農耕文化を脈々と育んできました。また,宍道湖・中海沿岸には,島根県都松江市や鳥取県西部の中心都市米子市をはじめ,山陰地方中央部の中核都市が集中しています。
神戸川の上流部は「島根県自然環境保全地域」に指定された女亀山や赤名湿地等,すぐれた自然が多く残っており,山間渓谷の様相を呈する中流部も、沿川に高さ100~200mの岸壁や岩柱が切り立ち「立久恵峡県立自然公園」に指定された優れた景観を誇っています。
TOPICS
やまたのおろちの正体!?
当時から洪水を繰り返していた斐伊川が、八つの頭を持つ大蛇(やまたのおろち)の正体という説もあります。
流れを変えた神戸川
神戸川は、「出雲国風土記」の時代には、神門川(かむどのがわ)と呼ばれ、出雲大川(いずものおおかわ)と呼ばれた斐伊川とともに、神門水海(かむどのみずうみ、現在の神西湖の前身)に注いでいました。斐伊川同様、上流域の「鉄穴流し(かんなながし)」と呼ばれた砂鉄採取に伴う廃砂による土砂流入や大きな出水により幾度も流れを変え、寛永年間の洪水を契機とした斐伊川の東流と元禄年間までに行われた松江藩の築堤工事により現在の流れとなったものです。
事務所リンク案内
斐伊川について更に知りたい方はこちらへ
お問い合わせ先
中国地方整備局
電話(082)221-9231(代表) 河川部