 |
| 用 語 集 |
 |
 |
|
 |
この用語集では、本書で使用される主要な用語を解説しました。
項目名に付した参照箇所──(植物)等──は、特にその分野に関わりの深い用語であることを示します。 |
 |
|
|
 |
| −は− |
| ■発情期 (はつじょうき) (ほ乳類) |
| ほ乳類が交尾可能な生理状態にある時期をいう。特に雌では卵巣の卵胞が成熟して排卵が始まり、発情ホルモンの分泌が盛んになる。 |
 |
| ■発生 (はっせい) (共通) |
| 多細胞生物が、卵から成長を開始して成体になるまでの過程をいう。 |
| また、上記の発生を「個体発生」とよび、生物全体が単純なものから複雑なものへと進化する過程を「系統発生」とよぶこともある。 |
 |
| ■パーマーク (魚類) |
| サケ科魚類の稚魚に出現する小判型の暗紫色の斑紋で、スモルト期には不明瞭になる。しかし、陸封型では成魚まで明瞭に残ることがある。 |
| →スモルト |
 |
| ■帆翔 (はんしょう) (鳥類) |
| 鳥の飛行方法のうち、上昇気流に乗って翼をいっぱいに広げて羽ばたきせずに飛行するエネルギー節約型の飛行法で、ワシタカ類、アホウドリなどの大型鳥が行なう。 |
 |
| ■半常緑樹 (はんじょうりょくじゅ) (植物) |
| サツキやツツジのように、春に伸びて夏に繁る春葉と、夏に伸びて一部は冬を越す夏葉の、2型の葉をもつ樹木をいう。 |
 |
| ■繁殖期 (はんしょくき) (共通) |
| 動物が交尾・産卵・出産・育児などの繁殖活動を行なう時期。1年のうち、一定の季節と関係して周期的に現れるものが多く、繁殖地への季節移動を伴うものもある。鳥類では、つがい形成、営巣、抱卵、育雛などの一連の行動が見られるが、つがい関係にも一夫一妻、一夫多妻、一妻一夫など様々なタイプがあり、雄と雌の役割分担も種によって異なる。 |
 |
| ■繁殖地 (はんしょくち) (鳥類) |
| 繁殖を行なう地域のことで、鳥類では留鳥と夏鳥がわが国で繁殖するが、旅鳥や冬鳥の多くは亜寒帯から北極にかけての寒冷地で繁殖する。 |
 |
| −ひ− |
| ■干潟 (ひがた) (共通) |
| 満潮時には冠水し、干潮時には露出する海岸の砂泥地。 |
| シギ・チドリ、サギ、ガン・カモなど、多くの鳥類の採餌場となる。 |
 |
| ■ひげ (魚類) |
| 魚類の口部周辺にある肉質の突起物で、一般に味覚器官である味蕾 (みらい)が密に分布している。淡水魚ではコイ科の一部とドジョウ科、ギギ科、ナマズ科、ヒレナマズ科に属する魚にヒゲが見られる。 |
 |
| ■雛 (ひな) (鳥類) |
| 孵化してから体羽が生えそろうまでの時期の鳥をいう。孵化時にすでに綿毛で覆われ、目も開いていて歩くことができる早成雛と、ほとんど丸裸で目も開かず、さらに数週間親の世話が必要な晩成雛とがある。 |
 |
| ■漂鳥 (ひょうちょう) (鳥類) |
| 山地や寒地で繁殖し、暖地で越冬する、国内レベルで短い渡りをする鳥をいう。 |
 |
| −ふ− |
| ■孵化 (ふか) (共通) |
| 卵がかえること。動物が卵内での発育を終了し、卵膜あるいは卵殻を破って外界に出て自由生活をするようになることをいう。孵化時の発生状態は、種によって大きな差がある。 |
 |
| ■不完全変態 (ふかんぜんへんたい) (昆虫) |
| 昆虫の変態様式のうち、卵→幼虫→成虫と変化し、蛹を経ないものをいう。 |
| →完全変態 |
 |
| ■複眼 (ふくがん) (昆虫) |
| 特殊な構造のレンズ眼である個眼が多数集合してできた眼で、節足動物 (甲殻類・昆虫類・剣尾類・唇脚類)に通常一対備わる。昆虫の複眼は短波長の光に敏感なのが普通で、紫外線にも感じ、色感覚能力、偏光分析能力も認められる。 |
 |
| ■淵 (ふち) (共通) |
| 淵は流れがゆるやかで水深が深いところで、水面は波立たず、底質はおおむね砂質である。 |
 |
| ■付着藻類 (ふちゃくそうるい) (昆虫・魚類) |
| 水中の構築物、岩、石礫、動植物などの表面に付着して繁茂する藻類 (主に珪藻、藍藻、緑藻)をいう。 |
 |
| ■冬鳥 (ふゆどり) (鳥類) |
| 秋に北方の繁殖地から渡来して越冬し、春に再び北方へ去る鳥をいう。 |
| →夏鳥 |
 |
| ■冬羽 (ふゆばね) (鳥類) |
| 鳥の非繁殖期の羽色で、夏羽 (生殖羽)より地味なことが多い。 |
 |
| ■分布 (ぶんぷ) (共通) |
| 動・植物が生活している範囲を地理的・空間的に示したもの。 |
 |
| −へ− |
| ■変態 (へんたい) (共通) |
| 動物が孵化して、成体とは別個な形態、生理および生態をもつ幼生 (幼虫)となる場合、幼生
(幼虫)から成体になるまでの過程を変態とよぶ。 |
| →完全変態、→不完全変態、 →ゾエア幼生 |
 |
| −ほ− |
| ■苞 (ほう) (植物) |
| 花のつぼみを被う小型の葉または花弁状のものをいう。 |
 |
| ■抱卵 (ほうらん) (鳥類、甲殻類) |
| 鳥では産卵後、孵化まで親鳥が卵を抱いて温めることをいう。また、エビやカニでは雌が受精卵を腹肢の毛につけて孵化まで抱えて保護することをいい、卵を付着させる腹肢の毛を抱卵毛、腹肢に卵を抱えている時期を抱卵期という。 |
 |
| ■保護色 (ほごしょく) (共通) |
| 動物の体色がその生息環境の色と似るように変化してい見分けにくくなるときの体色をいい、捕食者の目をくらまし、身を護ることができるとされるが、捕食者が周囲の環境と同様の体色に変化する場合も保護色とよぶことがある。 |
 |
| ■捕食 (ほしょく) (共通) |
| 肉食性動物が、生きている餌動物を捕らえて食することを捕食といい、捕食を行なう動物を捕食者という。 |
| →肉食性 |
 |
| ■ホバリング (鳥類) |
| 鳥類が飛翔しながら空中の1ヵ所に止まっている状態で、ハチドリが有名。 |
| 水辺の鳥ではカワセミやコアジサシが採餌の際に停空飛行を行い、獲物を見つけると真っ直ぐ水中にダイビングしてこれを捕らえる。 |

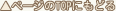 |