 |
| 用 語 集 |
 |
 |
|
 |
この用語集では、本書で使用される主要な用語を解説しました。
項目名に付した参照箇所──(植物)等──は、特にその分野に関わりの深い用語であることを示します。 |
 |
|
|
 |
| −た− |
| ■袋果 (たいか) (植物) |
| 乾果の一種で、1個の心皮からなる果実。熟すると心皮の合わせ目から裂開して種子が飛び出す。ガガイモなどがこのタイプ。 |
 |
| ■対生 (たいせい) (植物) |
| 葉のつき方の1つで、茎の節に2枚の葉が向かい合ってつくことをいう。 |
 |
| ■托葉 (たくよう) (植物) |
| 葉柄の基部や、基部が茎を抱く部分につく一対の葉に似た付属体で、葉の一部を構成するが、形や大きさには植物によって様々であり (エンドウ:大きな葉形、タデ科:葉鞘、ニセアカシア:刺状など)、これを欠く葉もある。 |
 |
| ■托卵 (たくらん) (鳥類) |
| ある生物種が他の生物種の産卵床に卵を産みつけ、孵化まで、あるいは孵化後も他の生物に保護してもらうことを托卵という。日本ではカッコウ属の鳥類に托卵の習性があることが知られているが、魚類でもムギツクがオヤニラミの巣に托卵することが報告されている。 |
 |
| ■脱皮 (だっぴ) (昆虫、甲殻類) |
| 昆虫・甲殻類など、固いキチン・クチクラ層を体表にもつ節足動物および線形動物が、成長の過程において古い外皮を一まとめに脱ぎ捨てる現象をいう。昆虫では幼虫時代に5〜7回、蛹で1回脱皮するのが普通であるが、カゲロウの幼虫は20回以上脱皮し、無翅昆虫では成虫も脱皮を続ける。また、甲殻類では一定の期間をおいて古い殻を脱ぎ捨て、その下に新しい殻を準備しておくという脱皮方法がとられるが、新しい殻は最初は軟らかいので一時的に体が大きくなることができ、それが堅くなるとまた脱皮が行なわれる。成長や変態は脱皮の際に行なわれる。 |
| なお、両生類やは虫類がその表皮を更新する現象も脱皮とよばれる。 |
 |
| ■旅鳥 (たびどり) (鳥類) |
| 北方の繁殖地と南方の越冬地を往復する渡りの途中、春秋にだけ日本に出現する鳥をいう。多くのシギ・チドリ類がこれに該当する。 |
 |
| ■たまり (共通) |
| 河川本流から独立して、陸域にある水たまりのこと。 |
 |
| ■単為生殖 (たんいせいしょく) (昆虫、魚類) |
| 本来は有性生殖を行なう種であるにもかかわらず、雌雄の配偶子の合一によらずに雌の配偶子 (卵子)が単独で個体を生ずる現象で、単性生殖、処女発生ともいう。単為生殖には、減数分裂により染色体数が半分になっているときに生じる半数単為生殖 (アリ、ミツバチ、スズメバチなど)や、通常の染色体数のときに生じる全数単為生殖 (アブラムシ、カイガラムシなど)が見られる。 |
| なお、ギンブナの雌性発生も単為生殖の一種である。 |
 |
| ■単眼 (たんがん) (昆虫) |
| 節足動物の眼のうち、複眼とは別に存在する簡単なレンズ眼をいう。複眼と併存する単眼は、光の信号を強化して中枢に送る働きをしている。 |
| →複眼 |
 |
| −ち− |
| ■稚魚 (ちぎょ) (魚類) |
| 魚の発育段階のうち、仔魚に続く段階で、すべての鰭 (ひれ)の条数が成魚のそれと同数になってから、鱗 (うろこ)ができ上がるまでの期間をいう。形態的には眼が大きかったり、鰭が長く伸びていたりして、細部のプロポーションが未成魚、成魚とは異なる。 |
 |
| ■地方名 (ちほうめい) (共通) |
| 生物には万国共通の学名および全国共通の和名がつけられているが、これとは別に、その地方特有の呼び名があり、これを地方名という。 |
 |
| ■柱頭 (ちゅうとう) (植物) |
| 被子植物の雌しべの先端の部分。花粉が付着しやすいように粘液を分泌する。 |
 |
| ■腸呼吸 (ちょうこきゅう) (魚類) |
| ドジョウ類が通常の鰓 (えら)呼吸のほかに、必要に応じて水面に浮上して空気を吸い込み、腸の上皮でガス交換を行なうことをいう。 |
 |
| ■沈水植物 (ちんすいしょくぶつ) (魚類) |
| 水生植物の1つで、根は水底に固着し、茎や葉は水面下にあるものをいう。花はマツモ科、イバラモ科の種では水中にあるが、その他の種では水面上に出るものが多い。 |
 |
| −つ− |
| ■つがい (鳥類) |
| 繁殖のためにカップルになる雌雄のこと。多くの鳥類では繁殖期を過ぎるとつがいを解消するが、非繁殖期にもつがいを続ける種もある。 |
 |
| ■翼 (つばさ) (鳥類) |
| 鳥類の前肢が空中の飛行用に変形・発達したもの。全体を覆う羽毛は風切羽 (飛羽)、雨覆羽 (翼覆)、小翼などに区別される。 |
 |
| ■ツンドラ (鳥類) |
| 極地の氷雪地帯と森林の北限の間で、寒冷なため森林が育たない荒れ地。北極海沿岸に見られる。永久凍土層が分布し、短い夏の間だけ地表の凍土が溶けて、コケ、地衣類、低木が生育する。シギ・チドリ類の多くは短い夏のツンドラ地帯で繁殖する。 |

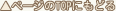 |
| −て − |
| ■底生動物 (ていせいどうぶつ) (魚類) |
| 水域で岩などに固着したり、砂泥中に潜入したり、あるいは水底上を這い回ったりして、水底から離れることなく生活している動物のことで、ベントスともいう。河川では水生昆虫、貝類、カニ類などがこれに該当する。 |
 |
| ■低木 (ていぼく) (植物) |
| 高木に比べて小さい、おおむね樹高2m以下の木本をいう。幹はあまり太くならず、下部から枝分かれして株立ちになるものが多い。 |
 |
| ■適応 (てきおう) (共通) |
| 生物のもつ形態学的ならびに生理学的性質が、その環境のもとでの生活に適合していること、または適合していく過程をいう。 |
 |
| ■デトリタス (デトライタス) (昆虫) |
| 有機残滓 (ざんし)ともいう。分解中の生物の断片や死骸をデブリといって、非生体的有機物であるが、これに付着したりこれを分解する微生物すなわち生体的有機物との区別・境界が困難であるので、総称してデトリタスまたはデトライタスという。多くの底生動物の重要な餌料となっている。 |
 |
| ■天敵 (てんてき) (ほ乳類) |
| 自然界で、ある生物種より食物連鎖の上位に位置し、その種の死亡要因として働く他の生物種を、その種の天敵という。 |
 |
| ■天然記念物 (てんねんきねんぶつ) (鳥類、ほ乳類) |
| 「学術上貴重で、わが国の自然を記念するもの」として、文化財保護法により保護されている貴重な動物植物および地質鉱物をいい、文部大臣が指定する国指定のものと、地方公共団体が指定するものがある。指定基準は動物については、地域を定めず指定したものと、地域を指定したものがある。 |
| また、世界的ならびに国家的に価値が特に高いものは、特別天然記念物に指定されている。 |
 |
| −と− |
| ■冬芽 (とうが) (植物) |
| 夏から秋につくられ、冬を越して春に伸びる芽をいう。寒さや乾燥に耐えるように鱗片に被われ、また、表面に?を分泌したり、毛が密生したりするものもある。 |
 |
| ■筒状花 (とうじょうか) (植物) |
| 花冠が管状になった花で、キクやヒマワリの花序の中心の部分やアザミなどがこれに該当する。 |
 |
| ■冬眠 (とうみん) (魚類、両性・は虫類、ほ乳類) |
| 動物が生活活動を中止した状態で冬を過ごすこと。本来は定温鉱物のうち、寒冷期になると体温が維持できずに低下してしまうリス・ムササビ・モルモット・ヤマネなどが、冬季に洞穴や木のうろの中などに入り、ほとんど動かずに春を待つ状態をいうが、広義には、体温が気温とともに低下し、体内の物質代謝が低下して活動に必要なエネルギーが得られなくなる陸生の変温動物(節足動物・陸生貝類・両生類・は虫類など)の越冬にも適用される。魚類ではウナギやドジョウなどが冬眠(生活活動を停止して泥に潜って過ごす)するほか、多くの種が深みに移動してじっとして過ごす。 |
 |
| ■毒牙 (どくが) (は虫類) |
| 毒蛇に特有の、毒腺と連絡した長く鋭い歯をいい、左右一対ある。毒牙には「溝牙」とよばれる溝を持つ構造のものと「管牙」とよばれる管状の構造のものの2種類があり、いずれも噛むと毒腺が圧迫され、歯の溝や管から毒液が出る。管牙を持つ種はマムシ、ヒャッポダ、ガラガラヘビ、ハブなど、溝牙をもつ種はコブラ、ウミヘビなどである。 |
 |
| ■土壌 (どじょう) (共通) |
| 土のこと。地殻の最表層にあり、細分された岩石が化学的・物理的および生物的に風化・分化したものに、動・植物の腐食物が混合してできたものをいう。 |
 |
| ■共食い (ともぐい) (魚類、両生類) |
| 動物が同種の他の個体を食べることで、肉食性動物ではしばしば観察される。 |

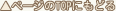 |