 |
| 用 語 集 |
 |
 |
|
 |
この用語集では、本書で使用される主要な用語を解説しました。
項目名に付した参照箇所──(植物)等──は、特にその分野に関わりの深い用語であることを示します。 |
 |
|
|
 |
| −や− |
| ■葯 (やく) (植物) |
| 雄しべの先端にある花粉をつくる袋形の器官。成熟すると裂けたり、一端に穴が開いたりして内部の花粉を放出する。 |
 |
| −よ− |
| ■蛹化 (ようか) (昆虫) |
| 完全変態の幼虫が終齢幼虫から蛹へ移行すること。蛹化は蛹化ホルモン (前胸腺ホルモン)の分泌によって促される。 |
 |
| ■葉鞘 (ようしょう) (植物) |
| 葉の基部が茎を包む鞘のようになっているものをいう。葉鞘はイネ科、タデ科などの植物に見られ、葉を支えるとともに茎を支える働きをしている。 |
 |
| ■幼鳥 (ようちょう) (鳥類) |
| 雛の体羽が生え揃ってから、第1回目の換羽を終えるまでの時期の鳥をいう。 |
| また、第1回目の換羽から成鳥羽に生え変わるまでの時期を若鳥という。第1回目の換羽で成鳥羽になるものもあるが、種によっては成鳥羽になるまでに数年かかるものもある。 |
 |
| ■葉柄 (ようへい) (植物) |
| 葉身を支える柄の部分で、葉身と茎・枝との連絡をするが、これを欠く葉もあり、無柄葉とよばれる。 |
 |
| ■翼鏡 (よくきょう) (鳥類) |
| 飛翔時の次列風切の開いた状態をいう。マガモでは大雨覆の先端と次列風切の先端がともに白いため、翼鏡の上下に白い線が出る。 |
 |
| ■翼帯 (よくたい) (鳥類) |
| 大雨覆の羽の先端の模様。先端で色が変化している場合は、翼を広げたときに帯状の模様になる。 |
 |
| ■ヨシ原 (よしはら) (鳥類) |
| ヨシの繁茂している場所。川では中〜下流域に多い。秋、冬のヨシ原は多くの陸鳥のねぐらに利用される。 |

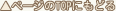 |