 |
| 用 語 集 |
 |
 |
|
 |
この用語集では、本書で使用される主要な用語を解説しました。
項目名に付した参照箇所──(植物)等──は、特にその分野に関わりの深い用語であることを示します。 |
 |
|
|
 |
| −み− |
| ■水際 (みずぎわ) (河川) |
| 河川や湖沼の水面と地表面が交わる部分をさしていう。一般に水際部は水域・陸域が入り組み、多様な環境のある場であって、生物の生息・生育上重要な役割を果たしている。 |
 |
| ■水鳥 (みずとり) (鳥類) |
| 水上を遊泳して生活する鳥類で、足には水掻きがある。アビ目、ミズナキドリ目、ペリカン目、ガンカモ目の各種と、チドリ目トウゾクカモメ科、カモメ科、ウミスズメ科に属する鳥がこれにあたる。 |
| →陸鳥、→水辺の鳥 |
 |
| ■水辺の鳥 (みずべのとり) (鳥類) |
| 水上を泳ぐことはないが、採餌、繁殖などに水辺を利用する鳥類で、サギ類、シギ・チドリ類のほか、セキレイ科、カワガラス科、ヒタキ科などの一部の鳥がこれに該当する。 |
| →陸鳥、→水鳥 |
 |
| ■未成魚 (みせいぎょ) (魚類) |
| 魚の発育段階のうち、稚魚に続く段階で、鱗 (うろこ)が形成されてから最初の成熟までの間をいう。形態的には成魚と変わらない。 |
| →稚魚 |
 |
| −め− |
| ■メガロッパ幼生 (メガロッパようせい) (甲殻類) |
| カニ類のメタゾエア幼生に次ぐ段階の幼生で、浮游生活から底生生活への移行期のもの。 |
| →ゾエア幼生 |
 |
| ■雌花 (めばな) (植物) |
| 雌性だけの生殖機能をもつ花で、雌しべがよく発達し、雄しべはないか、あっても退化して機能しないものをいう。 |
 |
| −も− |
| ■猛禽類 (もうきんるい) (鳥類) |
| 性格が猛々しく、小型の鳥類や小動物などを襲って食べる肉食性の大型鳥類をいう。主に、ワシタカ目、フクロウ目に属する鳥類がこれに該当する。ワシタカ目を「昼の猛禽」、フクロウ目を「夜の猛禽」とよんだりする。 |

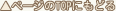 |