 |
| 用 語 集 |
 |
 |
|
 |
この用語集では、本書で使用される主要な用語を解説しました。
項目名に付した参照箇所──(植物)等──は、特にその分野に関わりの深い用語であることを示します。 |
 |
|
|
 |
| -ら- |
| ■落葉 (らくよう) (植物) |
| 高等植物において、葉柄の基部に離層が発達し、水分の供給が断たれ、葉が枯れて落ちる現象をいう。落葉前には葉の中の炭水化物、タンパク質、無機塩類などが茎に移動し、葉緑素が分解して黄変することが多い。 |
 |
| ■卵塊 (らんかい) (昆虫、貝類、両生類) |
| 複数の卵が一塊になって産出されている状態をいう。また、複数の卵が入っている卵嚢または複数の卵嚢の集団を卵塊をよぶこともある。 |
 |
| ■卵胎生 (らんたいせい) (貝類) |
| マムシやタニシのように、受精卵が親の体内に留まって発育し、親と同じ形になってから産出されること。卵のまま産出されるより減耗が少ない。 |
| →育児嚢 |
 |
| ■卵嚢 (らんのう) (甲殻類、両生類) |
| 卵を包んでいる丈夫な袋状のもので卵鞘 (らんしょう)ともいい、卵を外敵から保護したり、他物に付着させて固定したりする役割をする。本来の卵嚢は三次卵膜に相当するものが変化したものであるが、これらの他に、寒天質や泡状の物質が卵塊を包む場合も、これを卵嚢とよんでいる。 |
 |
| -り- |
| ■陸鳥 (りくちょう) (鳥類) |
| 繁殖、採餌、ねぐらなどの生活を、主として陸域で行なっている鳥をいう。 |
| 川を利用する鳥では、利用場所は主に高水敷や川辺林で、水面や水辺を直接利用することは少ない。 |
| →水鳥、→水辺の鳥 |
 |
| ■陸封型 (りくふうがた) (魚類) |
| 本来は海と淡水域の間を回遊していた魚が、淡水域で一生を過ごすようになったもので、ヤマメ、アマゴ、イトヨなどが代表的である。なお、1代限りの陸封型を河川残留型として区別することがある。 |
 |
| ■流域 (りゅういき) (河川) |
| ある川をとりまく土地において、降った雨が地表や地下水などを通じてその河川に流れ込むこととなる区域を、その河川の流域という。通常は、分水境
(分水嶺)がその境界となる。区域内の面積を流域面積または集水面積とよび、一般にk㎡で表す。 |
 |
| ■流下昆虫 (りゅうかこんちゅう) (魚類) |
| 落下昆虫に対して、水中を流れて来る昆虫をいう。落下昆虫は主に陸上の昆虫類
(水生昆虫の陸生の親も含む)であり、流下昆虫は主に水生昆虫である。 |
 |
| ■留鳥 (りゅうちょう) (鳥類) |
| 年間を通じて同一場所に止まって生活する鳥をいうが、一部、渡りや移動を行なうものもある。 |
 |
| ■両性花 (りょうせいか) (植物) |
| 1つの花に雄しべと雌しべを併せもつ花をいう。 |
| →単性花 |
 |
| ■林床 (りんしょう) (両生類) |
| 樹林の根元の、下草の生えているところをいう。 |
 |
| -る- |
| ■ルアー (魚類) |
| 小魚やカエル、昆虫などに似せた擬餌餌のこと (ルアーはおとりの意味)。 |
| 渓流釣りなどでよく用いられる。 |
 |
| -れ- |
| ■RDB (レッドデータブック:Red data book) (共通) |
| レッドデータブックは、絶滅のおそれのある野生生物の形態や生態、生育状況をまとめた本で、「生存に関して赤信号の灯った生物に関する各種の情報を記載した本」という意味である。1966年に国際自然保護連合
(IUCN)が絶滅のおそれのある動植物の現状を世界的な規模で明らかにしたのが最初で、その後、世界各国で独自の「レッドデータブック」が作成されている。 |
| 日本では環境庁が1989年に「緊急に保護を要する動植物の種の選定調査・結果概要」を発表している。日本版レッドデータブックとしては、1991年に脊椎動物
(日本産1,243種中283種)と無脊椎動物 (同33,776種中410種)のリストが刊行されており、掲載種は、絶滅種、絶滅危惧種、危急種、希少種および地域個体群に区分されている。また、1993年には日本植物分類学会により植物
(同約5,300種中895種)のリストが刊行されている。 |
 |
| ■レプトセファルス幼虫 (レプトセファルスようちゅう) (魚類) |
| ウナギ、アナゴなどの仔魚で、透明でヤナギの葉のような形をしており、扁平で体内に多量の水分を含む。浮力が大きく、水中をひらひらと漂いながら移動する。 |

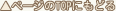 |