 |
| 用 語 集 |
 |
 |
|
 |
この用語集では、本書で使用される主要な用語を解説しました。
項目名に付した参照箇所──(植物)等──は、特にその分野に関わりの深い用語であることを示します。 |
 |
|
|
 |
| −さ− |
| ■採餌 (さいじ) (鳥類) |
| 鳥が餌をとること。およびその行為。 |
 |
| ■鰓葉 (さいよう) (昆虫) |
| 二枚貝の鰓 (えら)を構成する薄膜で、外套の内側に各側2枚ずつあり、呼吸をつかさどっている。 |
 |
| ■さえずり (鳥類) |
| 鳥がしきりに鳴くことをさえずりという。さえずりには次の2つの形がある。 |
| 1つはテリトリーソング (縄張りの歌)とよばれるもので、大声で単調な形式を繰り返すが、その調子は種独特なので、種の判別に役立つ。 |
| もう1つはコートシップソング (求愛の歌)とよばれるもので、小声で複雑に長々とやる。この鳴き方は小さえずえりともよばれ、幼鳥が餌をもらった後などにやるぐぜり鳴きによく似ている。 |
 |
| ■左岸 (さがん) (河川) |
| 河川の上流から下流に向かって見て左側にあたる岸をいう。 |
| →右岸 |
 |
| ■雑食性 (ざっしょくせい) (共通) |
| 動物が食物として植物質・動物質の双方を利用し、食物選択の幅が広いこと。 |
| 例えば魚類では、ウグイ、アブラハヤ、オイカワは落下昆虫・水生昆虫と藻類、コイ、ギンブナは水生昆虫・貝類と藻類、ドジョウ、ヨシノボリは水生昆虫と藻類などを摂餌する。 |
 |
| ■蛹 (さなぎ) (昆虫) |
| 完全変態をする昆虫の発育過程で、幼虫期と成虫期をつなぐ特殊な段階をいう。摂食や移動をしないので休止状態にあるように見られるが、内部で成虫の器官が作られている。 |
 |
| ■産卵管 (さんらんかん) (魚類) |
| 特定の場所に産卵するために、体外に長く伸びた輪卵管を産卵管という。二枚貝の鰓腔内に産卵する習性をもつ淡水産のタナゴ類やヒガイの雌に見られる。 |
 |
| ■産卵室 (さんらんしつ) (昆虫) |
| 昆虫が卵を産むための部屋。ケラは地表すれすれの土中に深さ2cm余りの部屋を作り、卵をかためて産む。 |
 |
| −し− |
| ■耳羽 (じう) (鳥類) |
| 鳥の顔面の頬の周囲にある羽毛で、耳孔を覆う。鳥の耳には外耳殻がなく、たんに外耳孔があるだけで、羽弁の疎らな耳羽がこれを覆っている。 |
 |
| ■仔魚 (しぎょ) (魚類) |
| 孵化してから、すべての鰭 (ひれ)の条数が成魚と同じ数になるまでの段階を仔魚という。 |
| →前期仔魚、→後期仔魚 |
 |
| ■歯舌 (しぜつ) (貝類) |
| 二枚貝類以外の軟体動物の口球 (消化管の先端のふくらんだ部分)内にある弾力のある強靭な帯状構造物で、ヤスリ様の小歯があり、正中線上のものを中央歯、その左右のものを側歯、その外側のものを縁歯とよぶ。口球の筋肉運動により口腔から突き出されて食物をかき取る働きをする。 |
 |
| ■自切 (じせつ) (は虫類) |
| 動物が敵により付属肢や尾などの体の一部を捕らえられたり破壊されたりした際に、その部分を自ら切断して放棄する現象をいう。自切はミミズ類、軟体類、カニ類、メクラグモ類、ガガンボ類、バッタ類など無脊椎動物に多く見られるが、脊椎動物でもトカゲなどは尾の自切を行なう。 |
 |
| ■地鳴き (じなき) (鳥類) |
| 鳥の鳴き方のうち、チッ、チッとかピピッというような、単音、2連音、3連音などの単純な鳴き声で、長くて複雑な繁殖期のさえずりと区別される。地鳴きの中には仲間に危険を知らせる警戒音のように、甲高いものもある。 |
 |
| ■指標種、指標生物 (しひょうしゅ、しひょうせいぶつ) (共通) |
| 生息に必要な環境条件の幅がごく狭い生物種 (ごく限られた環境条件の下でしか生息できない種で、狭適応種という)は、その種が存在することによって、場の物理化学的環境条件が狭い幅の中にあることを示す。このように、環境条件をよく示しうる種のことを指標種、その種に属する生物を指標生物という。 |
 |
| ■子房 (しぼう) (植物) |
| 被子植物の雌しべの下の脹らんだ部分。1〜数枚の心皮が結合して室をつくり、内部に胚珠を含む。受粉後、成熟すれば果実となり、胚珠は種子となる。 |
 |
| ■種 (しゅ) (共通) |
| 生物分類の基本単位で、形態的・生物学的形質が一定で、相互に交配可能である。例えば、人間はヒトHomo
sapiensただ一種で、「人間」は「種」ではない。 |
 |
| ■集団繁殖 (しゅうだんはんしょく) (鳥類) |
| 鳥がコロニーを形成して繁殖すること。 |
| →コロニー |
 |
| ■雌雄同体 (しゆうどうたい) (貝類) |
| 一般に高等植物では雌雄は別の個体である (雌雄異体という)が、環形動物や軟体動物 (巻貝類・二枚貝)の中には雌と雄の性質を1個体で兼ね備えているものがあり、これを雌雄胴体という。 |
| 雌雄同体の場合でも、通常は異なる個体との間で交接が行なわれ、互いに他の個体と精子を交換し合って繁殖し、自家受精によって繁殖することは少ない。 |
 |
| ■終齢幼虫 (しゅうれいようちゅう) (昆虫) |
| 完全変態の昆虫ではサナギになる直前の幼虫をいい、不完全変態の昆虫では羽化の直前の幼虫をいう。また、終齢幼虫の1つ前の段階を亜終齢幼虫とよぶ。チョウなどでは2齢〜亜終齢までの幼虫は形態的に似ており、脱皮を確認しないと齢数を確認できない場合が多い。 |
 |
| ■春葉 (しゅんよう) (植物) |
| 春に伸びて夏に繁る葉で、夏に伸びて越冬する夏葉と区別される。サツキやツツジでは春葉と夏葉の形状が異なる。 |
 |
| ■小穂 (しょうすい) (植物) |
| イネ科やカヤツリグサ科の花序の基本になる部分で、外側を2枚の苞頴 (ほうえい・第一苞頴、第二苞頴とよばれる)が包み、その中に1〜数個の小花がある。1つの小花には2枚の頴 (外側を護頴、内側を内頴とよぶ)がある。 |
 |
| ■常緑樹 (じょうりょくじゅ) (植物) |
| 葉が形成されてから冬を越冬し、1年以上落ちないで葉の働きをする樹木をいう。葉の寿命が1年以上あり、新葉が出てから古い葉が落ちる。針葉樹と広葉樹があり、針葉樹は亜寒帯に多く、広葉樹は温帯から熱帯にかけて多い。 |
 |
| ■食害 (しょくがい) (鳥類) |
| 動物が森林や農作物を食い荒らして害を与えること。食害を起こす動物を害虫、害鳥、害獣などとよぶ。 |
 |
| ■食餌植物 (しょくじしょくぶつ) (昆虫) |
| チョウ目の昆虫の幼虫の食物となる植物をいう。科・属などで一定の傾向が見られ、進化の過程で変化してきたことが推定されている。食餌植物のうち、樹木を食樹、草本を食草、あるいは両者を一緒にして食草とよぶこともある。 |
 |
| ■食樹・食草 (しょくじゅ・しょくそう) (昆虫) |
| チョウやガなどの昆虫の幼虫が決まって餌としている木本や草本をいう。 |
| 例えば、国蝶のオオムラサキはエノキなどを食樹とし、マダラミズメイガはジュンサイなどを食草としている。 |
 |
| ■食性 (しょくせい) (共通) |
| 動物が習性上、どのような種類の食物を取るかを示す用語。食性は一般に、植食性、肉食性、雑食性、腐食性に分けられる。 |
 |
| ■シラスウナギ (魚類) |
| ウナギの葉形幼生が変態してウナギ型になったもので、全長は50〜60mm、色素が未発達のため無色透明に近い。シラスウナギが沿岸や河口に現れるのは10月頃からで、産卵から4〜5ヵ月を経過している。シラスウナギは昼間は沿岸や河口の底土や礫の間などに隠れて過ごし、夜間に浮上して河を溯上する。溯上期になると色素が発達してクロコに変化する。 |
| →クロコ |
 |
| ■シルト (河川) |
| 堆積物の粒径を表す分類名で、一般に0.074〜0.005mmの範囲の粒径を指す。0.005mm以下のものは粘土、0.001mm以下のものをコロイドとして分類する。 |

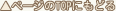 |
| −す− |
| ■水系 (すいけい) (河川) |
| 河川は上流山地の水源から海に至るまで、支川等を含めた一連の系としての流路を形成している。本流、支流、派川およびこれに接続している湖沼等によって形成される1つのまとまりを水系という。 |
 |
| ■水生昆虫 (すいせいこんちゅう) (昆虫、魚類) |
| 生活史の全部または一部を水中で生活する昆虫のグループの総称。水中に生息する昆虫は本来すべて陸生で、2次的に水中生活に移ったものと考えられている。昆虫綱のうち、水生生活をする種が見られる目は、トビムシ目、ゴキブリ目、カワゲラ目、カゲロウ目、トンボ目、カメムシ目、アミメカゲロウ目、トビケラ目、チョウ目、コウチュウ目、ハチ目、ハエ目の12目である。このうち、成虫も幼虫も水中で過ごす種が見られるのはカメムシ目とコウチュウ目(但し、コウチュウ目のホタル科、ナガハナノミ科の成虫は陸生)だけで、その他の目に属する種では幼虫、あるいは幼虫と蛹の時代を水中で過ごし、成虫になると水から出て陸上(空気中)で生活する。 |
 |
| ■水草 (すいそう・みずくさ) (昆虫・魚類) |
| 主に淡水域に生育する大型高等植物の総称で、水生植物ともいう。生活場所や生活型によって、抽水植物、浮葉植物、沈水植物、浮游植物などに分けられる。 |
 |
| ■巣立ち (すだち) (鳥類) |
| 雛が成長して巣を離れること。巣を離れた段階で自立して生活できる種もあるが、まだ飛べない状態で巣立つ種もある。後者は早成雛とよばれ、巣立ち後もしばらくは親が給餌して飛べるようになるまで世話をする。 |
 |
| ■棲み分け (すみわけ) (共通) |
| 生活様式がよく似ており、環境に対する要求の似た近似種が、空間的あるいは時間的に生活の場を異にしている現象をいう。また、同じ生活の場を占める場合には食物の種類を異にすることが多く、これはときに『食い分け』とよばれる。 |
 |
| −せ− |
| ■瀬 (せ) (共通) |
| 河川では水深が浅くて流れが急なところをいい、早瀬と平瀬に分けられる。 |
| 早瀬:流れは速く、水面には白波が立つ。底質はおおむね浮石である。 |
| 平瀬:流速は早瀬よりはやや遅く、水面にはしわのような波が立つ。底質はおおむね沈み石である。 |
 |
| ■生活型 (せいかつがた) (共通) |
| 生物を生活様式に基づいて類型化したもの、ないしは生活様式による生物の類型をいい、生活様式に着目した生物のグループ分けや、肉食性、植物性、雑食性といった分け方がこれに該当する。 |
 |
| ■成魚 (せいぎょ) (魚類) |
| 魚類の発育段階のうち、未成魚に続く最後の段階で、性的に成熟してからをいう。 |
 |
| ■成虫 (せいちゅう) (昆虫) |
| 昆虫およびクモ類の成体をいい、幼虫から変態・成長したもので、生殖能力をもつ。昆虫では羽がある個体はいずれも成虫である。 |
 |
| ■性転換 (せいてんかん) (魚類) |
| 発育に応じて雄から雌、雌から雄と性が変わる現象をいう。クロダイなどでは最初は雄、成熟すると雌に変わる。タウナギ、ハタ類では最初は雌で、やがて雄に変わる。 |
 |
| ■成葉 (せいよう) (植物) |
| 若葉が十分に伸びて、所定の大きさまで生長した葉をいう。 |
 |
| ■堰 (せき) (河川) |
| 河川を横断して設けられる構造物で、その目的により取り入れに必要な水位を確保するための取水堰、河口付近で満潮時や渇水時に塩水が溯上するのを防ぐ潮止堰、流水の分流を計画どおり行なわれるようにする制御分流堰がある。 |
| 普段ゲートを閉めて流水を堰き止め、農業用水や都市用水に利用されるが、洪水時にはゲートを全開して洪水をスムーズに流す。 |
 |
| ■腺 (せん) (植物) |
| 植物の表皮系に見られる分泌細胞をいう。葉面や花の蜜腺などにあたり、樹脂や粘液質、揮発性油などを分泌する。 |
 |
| ■腺体 (せんたい) (植物) |
| 植物の表皮系に見られる腺構造の細胞の集合体。ヤナギ類では花被は著しく退化して腺体となっているものが多い。 |
 |
| ■腺毛 (せんもう) (植物) |
| 上記の腺構造のうち、特に毛の形をしたものをいう。単細胞性 (分泌細胞)と多細胞性 (分泌組織)のものとがあり、棒状または盤状で、活発に分泌する腺毛の細胞には豊富な原形質と分泌物が認められる。 |
 |
| −そ− |
| ■総苞 (そうほう) (植物) |
| 花序の基部に多数ついている苞 (花のつぼみを被う小型の葉や花弁状のもの)をいう。アザミ、タンポポなどキク科植物によく見られる。 |
 |
| ■ゾエア幼生 (ゾエアようせい) (甲殻類) |
| 十脚甲殻類 (エビ・カニ・ヤドカリ類)の幼生期で、受精卵からノウプリウス、メタノプリウスの次の幼生期をいい、脱皮したのちメタゾエアを経てメガロッパになる (エビ類ではこの発育段階をミシス期、ヤドカリ類ではグロウコトエ期という場合もある)。多くの十脚類では孵化はゾエア期またはメタゾエア期で起こるが、サワガニのような半陸生種では稚ガニになるまで抱卵している。 |
 |
| ■属 (ぞく) (共通) |
| 生物分類段階の1つで、共通の形質を持つ種をまとめた単位。多くの種をゆるやかに1属に含める粗分的な立場と属の範囲を狭くとる細分的な立場をとる人によって1属に含まれる種類が異なるのは、科や目などの上位分類群の場合と同様である。 |
 |
| ■側歯 (そくし) (貝類) |
| 二枚貝ハマグリ目の両殻片の内側にある蝶番線に沿った突起のうち、殻頂の真下にある主歯に対して殻頂から離れたところにあるものを側歯といい、前方にあるものを前側歯、後方にあるものを後側歯とよぶ。 |
 |
| ■側線 (そくせん) (魚類) |
| 魚類の体側の皮下を走っている皮膚感覚器官をいうが、実際にはこの感覚器官が体表に開孔している小孔をさして側線といっている。魚類は視覚が効かない場合も側線感覚で障害物などを避けることができる。 |

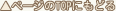 |