 |
| 用 語 集 |
 |
 |
|
 |
この用語集では、本書で使用される主要な用語を解説しました。
項目名に付した参照箇所──(植物)等──は、特にその分野に関わりの深い用語であることを示します。 |
 |
|
|
 |
| −か− |
| ■花冠 (かかん) (植物) |
| 花弁 (花びら)の集まりをいう。種子植物の構成要素の1つで、萼の内側に生じ、雄しべ、雌しべを護る。花冠には花弁が互いに癒合した合弁花冠と、花弁が分離した離弁花冠がある。 |
 |
| ■学名 (がくめい) (共通) |
| 国際命名規約にのっとり生物につけられる属名と種名の2語からなる名称 (例外的に亜種の場合は3語)。属名はラテン語またはラテン語化した名詞、種名・亜種名は形容詞で、同種異名、異種同名は禁じられている。なお、科より上の分類単位 (目、綱、門等)は1語で表す。 |
| コイ科:Cyprinidae |
| モロコ亜科:Barbinae |
| タモロコ属:Gnathopogon |
| 種 (ホンモロコ):Gnathopogon elongatus |
| 亜種 (タモロコ):Gnathopogon elongatus elongatus |
 |
| ■花茎 (かけい) (植物) |
| 花をつける茎をいう。 |
 |
| ■飾り羽 (かざりばね) (鳥類) |
| 繁殖期にシラサギ類の胸や肩羽に生じる長い毛状の羽をいう。非繁殖期には消失する。 |
 |
| ■花糸 (かし) (植物) |
| 雄しべの葯を支えている細長い部分。 |
 |
| ■果実 (かじつ) (植物) |
| 種子植物の花が成熟してできたものの総称で、子房が成熟してできた真果と、花床や萼筒など子房以外のものを含めて成熟した偽果とがある。 |
 |
| ■河床 (かしょう) (河川) |
| 河川の底の部分をいう。一般には流水の流れている水面に対応した底の部分を指すが、河川計画においては計画上の洪水が流下する水面に対応する底の部分を指す。 |
 |
| ■花穂 (かすい) (植物) |
| 花が穂のように集まって咲いている形。穂状花序、総状花序などをいう。 |
 |
| ■河川改修 (かせんかいしゅう) (河川) |
| 河川に適切な河床の勾配と、それに対応した断面を与えることにより、高 (洪)水時の流量を安全に流下させ破堤などで生じる被害 (水害)を防止すること。 |
| 同時に流域からの出水を適切に河川へ排水し、堤内地の湛水被害を防止するような河川工事もこれに含める。 |
 |
| ■花柱 (かちゅう) (植物) |
| 雌しべの柱頭と子房の中間の細長い部分をいう。 |
 |
| ■滑翔 (かっしょう) (鳥類) |
| 鳥が羽ばたきせずに、空中を滑るように飛ぶこと。トビの飛翔がこのタイプ。 |
 |
| ■河畔林 (かはんりん) (河川) |
| 河川の水際や河川沿いに存在する樹林をいう。 |
| 一般に、平野部の蛇行河川に沿った樹林帯を河畔林とよび、山間部の渓流沿いの樹林帯を渓畔林とよぶ。なお水防などの目的で植えつけられたものは水害防備林という。 |
 |
| ■花粉 (かふん) (植物) |
| 種子植物の雄しべの葯の中にある粉状の生殖細胞。 |
 |
| ■花柄 (かへい) (植物) |
| 花序をつくる枝で、花をつけている柄の部分をいう。花梗 (かこう)ともいう。 |
 |
| ■果胞 (かほう) (植物) |
| カヤツリグサ科スゲ属の雌花を包む袋状の前葉 (苞の腋から出た枝の第1の葉)をいう。スゲ属では花には花被がなく、雌花はおのおの果胞とよばれる小さな袋の中に1個ずつ着き、柱頭は2〜3個で、果胞の先端の小穴から外出し、風によって受粉し、小型の果実となる。 |
 |
| ■河原 (かわら) (河川) |
| 河道内の自然地形で、増水時には水没するが、通常は露出している砂や石の多い平地をいう。 |
 |
| ■桿 (かん) (植物) |
| 大型のイネ科植物 (メダケ、ネザサ、アイアシなど)の茎をいう。しばしば木化している。 |
 |
| ■冠羽 (かんう) (鳥類) |
| 鳥類の頭頂から後ろにかけて生えている冠状の長い羽毛。羽冠ともいう。 |
| 河川・水辺の鳥ではサギ科、ガンカモ科、チドリ科、カワセミ科 (ヤマセミ)、ヒバリ科、ホオジロ科などの種類に見られる。 |
 |
| ■乾果 (かんか) (植物) |
| 果実のうち、種皮が乾燥して薄いものをいう。乾果には果実が熟しても裂けない閉果と、熟すると一定の場所で裂ける裂開果がある。 |
 |
| ■完全変態 (かんぜんへんたい) (昆虫) |
| 昆虫の変態の様式のうち、卵→幼虫→蛹→成虫と変化するもの。 |
| →不完全変態 |

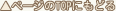 |
| −き− |
| ■帰化植物 (きかしょくぶつ) (植物) |
| 本来の野生地から、人間の移動や動物の媒介によって他の地域に持ち込まれ、自然に定着した植物をいう。イネ科、マメ科、アブラナ科、ナス科などの種に多い。 |
 |
| ■危急種 (ききゅうしゅ) (共通) |
| レッドデータブックでの選定権のうち、生息地の大部分で生息条件または生息環境が悪化しており、近い将来、絶滅危惧のランクに含まれる可能性が大きい種または亜種をいい、脊椎動物50種、無脊椎動物64種、植物678種がリストアップされている。 |
| →レッドデータブック |
 |
| ■擬傷 (ぎしょう) (鳥類) |
| 繁殖期に、外敵の眼を雛から逸らすために、親鳥が傷ついたふりをすること。 |
| コチドリ、ヒバリなど、地上で雛を育てる鳥に見られる。 |
 |
| ■希少種 (きしょうしゅ) (共通) |
| レッドデータブックの選定権のうち、分布地や生息域が限定されている種または亜種をいい、脊椎動物139種、無脊椎動物276種がリストアップされている。 |
| →レッドデータブック |
 |
| ■寄生 (きせい) (共通) |
| 異種の生物が一緒に生活している現象のうち、一方 (寄生者)が利益を受け、他方 (寄主、宿主)が何らかの害を受けているものをいう。寄生のうち、寄生者が宿主の体内に侵入して生活するものを内部寄生、宿主の体表に付着して生活するものを外部寄生、寄生者が宿主を離れて生活することがまったく不可能な場合を無条件寄生、寄生生活・自由生活のいずれも可能な場合を不完全寄生または任意寄生という。なお、寄生は生きている生物間の関係をいう。 |
 |
| ■基底 (きてい) (魚類) |
| 背鰭 (せびれ)、臀鰭 (しりびれ)などの、鰭 (ひれ)の付け根の部分をいう。 |
 |
| ■気門 (きもん) (昆虫) |
| 昆虫その他、気管呼吸を行う無脊椎動物の体表にある呼吸門 (空気の出入口)をいう。普通の昆虫では胸部に2対、腹部に8対の気門がある。 |
 |
| ■給餌 (きゅうじ) (鳥類) |
| 親鳥が雛に餌を与えること。孵化後から巣立ちまで餌を運ぶが、種によっては巣立ち後も雛に給餌する。 |
 |
| ■吸虫類 (きゅうちゅうるい) (その他) |
| 扁形動物吸虫綱に属する生物の総称。すべて寄生性で、ヒトをはじめ多くの動物の肺や肝臓などに寄生し、被害をもたらすものもある。体は扁平な卵円形で頭部と腹部中央に吸盤があり、この吸盤で宿主に吸着する。住血吸虫、双口吸虫、肺吸虫など多くの吸虫類が河川水辺の魚介類、両生類、鳥類、ほ乳類等を中間宿主としている。 |
 |
| ■鋸歯 (きょし) (植物) |
| 葉の縁が鋸の歯のように細かく切れ込んだ状態を言う。切れ込みの深さや形状により、鈍鋸歯縁、鋸歯縁、歯牙縁、重鋸歯縁などに分類される。 |
 |
| ■魚道 (ぎょどう) (河川) |
| 堰やダムなどの横断工作物において、その本体が魚類等の通過を妨げる場合、これを可能とする施設をいい、階段状のもの、ゆるい傾斜のものなどがある。 |

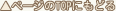 |
| −く− |
| ■嘴 (くちばし) (鳥類) |
| 鳥類の口先で、上下の顎が角質の鞘でおおわれて突出したもの。 |
| 嘴の形状は分類グループにより共通の特徴があり、その形でおおまかな分類が可能である。また、嘴の形は鳥の食性をよく反映しているため、生活形の代表とされている。 |
 |
| ■クロコ (魚類) |
| 外洋で孵化したウナギは葉形幼生 (レプトセファルス)→シラスウナギと変態して沿岸に近づき、秋から春にかけて川に溯上する。溯上期のウナギは色素が発達して体色が黒くなるので、クロコとよばれる。 |
| →シラスウナギ |
 |
| −け− |
| ■堅果 (けんか) (植物) |
| 乾果の一種で、クリ、カシ、シイなどのように果皮が木質で堅く、種子からよく離れるものをいう。 |
 |
| −こ− |
| ■降海型 (こうかいがた) (魚類) |
| 陸封型 (本来は海と淡水域の間を回遊していた魚が淡水域で一生を過ごすようになったもの)が存在する種の中で、本来の海と淡水域を往復する性質を維持している個体を降海型という。サツキマス (アマゴ)、サクラマス (ヤマメ)、ウグイ、イトヨなどが代表的である。 |
| →陸封型 |
 |
| ■後期仔魚 (こうきしぎょ) (魚類) |
| 孵化直後の仔魚は、まだ口が開かず、鰭 (ひれ)もなく、腹部にある大きな卵黄を栄養としているが、卵黄を吸収し尽くす頃には口が開いて自分で餌をとるようになり、次第に鰭が形成されていく。このうち、孵化してから卵黄を吸収し尽くすまでを前期仔魚、その後、鰭の条数が親と同じになるまでを後期仔魚という。 |
| →仔魚、→前期仔魚 |
 |
| ■洪水 (こうずい) (河川) |
| 豪雨などにより、普段の何十倍から何百倍もの水が流れる現象をいう。あふれるかあふれないかとは別問題である。 |
| 洪水の起こる原因の大部分は降水によるが、その他突発的な山くずれや雪崩などにより起こる場合もある。 |
 |
| ■高水敷 (こうすいしき・こうずいじき) (河川) |
| 河道のうち、普段は冠水せず洪水時のみ流水が流れる部分をいう。通常はグランド・公園・農地などに利用されていることが多い。 |
| →低水敷 |
 |
| ■行動圏 (こうどうけん) (共通) |
| 動物の個体が採食・生殖・育仔という通常の活動をするために動き回る範囲で、毎日の遊動ルートを長期間に集積し、その最外周を線で結んだものとして表現される。行動圏は、その内部に他個体が自由に侵入することができる点で、縄張りとは区別される。 |
 |
| ■高木 (こうぼく) (植物) |
| 幹が太く高く、中部以上から枝を出し、芽が地上数メートルより高いところに出るものをいう。非常に大きくなるもの (高さ20m以上)を大高木といい、小さいものを小高木というが、その区別はそれほど明確ではない。 |
 |
| ■護岸 (ごがん) (河川) |
| 堤防あるいは河岸が流水による侵食や水が内部に浸透することなどを原因に破壊にいたることを防護するための構造物。 |
| 一般に法覆 (のりおおい)工、法止 (のりどめ)工、根固 (ねがため)工からなる。 |
| コンクリート、石、杭、樹木などいろいろな材料が用いられる。 |
 |
| ■互生 (ごせい) (植物) |
| 葉のつき方の1つで、葉の節に互いちがいに1枚ずつつくものをいう。 |
 |
| ■コロニー (鳥類) |
| コロニーは、同一種または若干種の生物の集まりが一地域をある程度恒常的に占めている状態を、広い意味で社会的なニュアンスをもって意味する言葉で、その集団の性質により、永続的コロニー、繁殖コロニー、季節的コロニーなどに区別される。鳥類の場合には、数多くの鳥が1ヵ所に集まって繁殖する場の意味で使用されている。水辺の鳥では、サギ類、チドリ類、アジサシ類などがコロニーを形成する。 |
 |
| ■婚姻色 (こんいんしょく) (魚類、その他) |
| 魚類、両生類、は虫類、鳥類では、繁殖期なると体色の一部または全体が著しい変化を来し、通常の体色に比して華麗な色調をもつようになる。この着色部は求愛行動のときに異性に見せびらかされ、性行動が触発されるので婚姻色とよばれる。例えば、ニホントカゲでは交尾期に雄の喉から腰にかけてオレンジ色の婚姻色が現れる。魚では雌雄に現れるウグイ、マルタウグイ、サケなど、雄に特に強く現れるゼゼラ、モツゴ、ヨシノボリ類、アブラハヤ、オイカワ、カワムツなど、雌に強く現れるウキゴリ、ビリンゴなどがある。 |
 |
| ■根茎 (こんけい) (植物) |
| 地下茎の一種で、タケ、ヨシ、シバなどのように、横に長く伸びて新しい茎を作るものをいう。 |

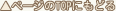 |