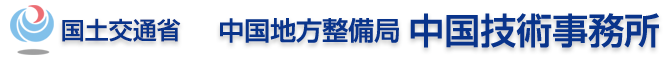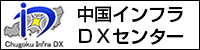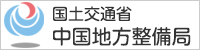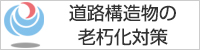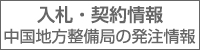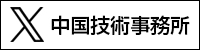平成18年度(2006年)中国地方建設技術開発交流会
メインテーマ
生活を豊かにする新しい技術
発表テーマ
「環境」「コスト縮減」「安全」
※ 課題の![]() をクリックすると、配付資料がご覧頂けます。
をクリックすると、配付資料がご覧頂けます。
※ 諸事情により公表されてない資料もあります。
鳥取県会場
| 課題名 | 協会名等 | 発表者 |
| 基調講演 | ||
| 河川における土砂管理について |
鳥取大学 | 工学部 土木工学科 檜谷 治 |
| 学官の技術研究開発の成果発表 | ||
| ストック型社会構築に向けた持続可能な建築のあり方 |
鳥取環境大学 | 環境情報学部 環境デザイン学科 木俣 信行 |
| 市瀬地区の地すべり崩落とその対策工 |
鳥取県 | 八頭総合事務所 県土整備局 西尾 雅明 |
| 民間開発新技術発表 | ||
| ごみ溶融スラグを利用したアスファルト舗装技術 | (社)日本土木工業協会 | (株)大林組 日笠山 徹巳 |
| 高炉スラグ微粉末を用いた高耐久性PC構造物 |
(社)プレストレスト・コンクリート建設業協会 | (株)安部日鋼工業 堀尾 哲也 |
| RTK-GPS・自動追尾光波測定器(T/S)による盛土の転圧回数 管理システム |
(社)日本建設機械化協会 | 西尾レントオール(株)杉山 忠 |
| 都市再生に寄与する鋼矢板新規用途開発への取り組み) |
(社)日本鉄鋼連盟 | 鋼管杭協会 永尾 直也 |
| DRIM(ドリム)を用いた漂砂制御技術 |
(社)日本埋立浚渫協会 | 若築建設(株)山口 洋 |
| 活用後の新技術・新工法工事事例発表 | ||
| 河川堤防における雑草を抑制する手法検討について |
国土交通省 | 中国技術事務所 山形 勝巳 |
| 技術開発支援制度による研究発表 | ||
| コスト削減を目指したヴァーチャル型技術開発法の提案 |
岡山大学大学院 | 環境デザイン工学科 谷口 健男 |
| 技術開発支援制度による研究開発課題への照会等の窓口は、(社)中国建設弘済会(TEL082-221-6462)となっています。 | ||
島根県会場
| 課題名 | 協会名等 | 発表者 |
| 基調講演 | ||
| 新技術開発と地域環境-中海・宍道湖を例として- |
島根大学 | 総合理工学部 三瓶 良和 |
| 学官の技術研究開発の成果発表 | ||
| 島根県における耐候性鋼橋梁の腐食実態と新しい現地適用性 評価の試み |
松江工業高等専門学校 | 環境・建設工学科 大屋 誠 |
| 民間開発新技術発表 | ||
| 仮設用鋼製函体を用いたNDR工法 |
中国土木施工管理 技士会連合会 | 五洋建設(株)佐々木 広輝 |
| 水塊の攪拌混合及び曝気による水質浄化装置 |
建設業協会 中国ブロック協議会 | (株)共立 篠原 剛 |
| 建設汚泥を建設資材に再資源化 |
(社)日本土木工業協会 | 泥土リサイクル協会 野口 真一 |
| 常温硬化型路面補修材スラリーパック |
(社)日本道路建設業協会 | 大林道路(株)鈴木 徹 |
| 視覚障害者誘導用ブロック型音声案内装置「ブロックボイス」について |
(社)日本道路建設業協会 | 日本道路(株)工藤 友行 |
| 活用後の新技術・新工法工事事例発表 | ||
| メタルロード工法について |
国土交通省 | 斐伊川・神戸川 総合開発工事事務所 板持 光雄 |
| 竹割り型土留め工法の計画、設計、施工について |
島根県 | 浜田河川総合開発事務所 三上 利雄 |
| 技術開発支援制度による研究発表 | ||
| 石炭灰造粒物を用いた底質改善技術の開発 |
広島大学大学院 | 工学研究科 日比野 忠史 |
| 技術開発支援制度による研究開発課題への照会等の窓口は、(社)中国建設弘済会(TEL082-221-6462)となっています。 | ||
岡山県会場
| 課題名 | 協会名等 | 発表者 |
| 基調講演 | ||
| 森林生態系の炭素固定の仕組み -森林における炭素収支野外観測から分かったこと- |
岡山大学大学院 | 環境学研究科 山本 晋 |
| 学官の技術研究開発の成果発表 | ||
| 現地計測データを利用した軟弱地盤の変位予測 |
岡山大学大学院 | 環境学研究科 西村 伸一 |
| 旧日銀岡山支店本館耐震・改修工事について |
岡山県土木部 | 都市局建築営繕課 中野 弘一朗 |
| 民間開発新技術発表 | ||
| 塩化物イオンコンクリートへの浸透予測に関する研究 |
中国土木施工管理 技士会連合会 | アイサワ工業(株)細谷 多慶 |
| 城郭石垣の維持管理技術 |
(社)日本土木工業協会 | (株)間組 笠 博義 |
| 工事渋滞を低減する急速施工立体交差技術「すいすいMOP工法」について |
(社)日本橋梁建設協会 | 三菱重工 橋梁エンジニアリング (株)山内 誉史 |
| 島根県におけるボーリング情報公開システムについて |
(社)建設コンサルタンツ 協会 | 中央開発(株)王寺 秀介 |
| 新世代鋼矢板「ハット形鋼矢板900」 |
(社)日本鉄鋼連盟 | 鋼管杭協会 辻本 和仁 |
| 活用後の新技術・新工法工事事例発表 | ||
| ナローマルチビームによるダム湖の地形測量 |
国土交通省 | 苫田ダム管理所 長谷川 貴一 |
| 技術開発支援制度による研究発表 | ||
| 小型ヘリコプター撮影画像を利用した中国地方の低コスト防災調査技術開発に関する研究 |
広島大学大学院 | 工学研究科 作野 裕司 |
| 技術開発支援制度による研究開発課題への照会等の窓口は、(社)中国建設弘済会(TEL082-221-6462)となっています。 | ||
広島県会場
| 課題名 | 協会名等 | 発表者 |
| 基調講演 | ||
| 最近の水災害の特徴と今後の減災対策 |
広島大学大学院 | 工学研究科 河原 能久 |
| 学官の技術研究開発の成果発表 | ||
| 水災害対策支援のための高精度氾濫流シミュレータの開発 |
広島大学大学院 | 工学研究科 内田 龍彦 |
| 民間開発新技術発表 | ||
| 建設系汚泥を核とした資源循環モデルの構築(リサイクル製品の有効な活用方法)について |
中国土木施工管理 技士会連合会 | (株)熊野技建 小田原 卓哉 |
| 山地降雨流出予測解析システム |
(社)日本土木工業協会 | 鹿島建設(株)小田切 光典 |
| 超高強度繊維補強コンクリート「ダクタル」を用いたプレストレストコンクリート橋梁 |
(社)日本土木工業協会 | 大成建設(株)武者 浩透 |
| N型流木捕捉工について |
(社)日本鉄鋼連盟 | 日鐵建材工業(株)大隅 久 |
| 生分解ドレーン材を用いたネットワークドレーン工法 |
(社)日本埋立浚渫協会 | 国土総合建設(株)深澤 薫 |
| 活用後の新技術・新工法工事事例発表 | ||
| 舗装工事における新技術を活用したコスト縮減・環境対策事例 |
国土交通省 | 広島国道事務所 大田 和正 |
| 泥上でのトレンチャー型地盤改良工法 |
工事発注機関 | 広島県福山地域事務所建設局 中本 俊幸 |
| 技術開発支援制度による研究発表 | ||
| 携帯型貫入試験機による風化急斜面の地盤強度の評価と危険度判定への応用に関する研究 |
広島大学大学院 | 工学研究科 土田 孝 |
| 技術開発支援制度による研究開発課題への照会等の窓口は、(社)中国建設弘済会(TEL082-221-6462)となっています。 | ||
山口県会場
| 課題名 | 協会名等 | 発表者 |
| 基調講演 | ||
| 安全で、安心して暮らせる地域づくりを支える新しい技術-地域防災対策支援システム- |
山口大学 | 地域共同研究開発センター 近久 博志 |
| 学官の技術研究開発の成果発表 | ||
| 生物の増殖を妨げる堰や落差工の改修方法に関する研究 |
独立行政法人 | 水産大学校 浜野 龍夫 |
| 山口県切羽評価システムを使用した補助工法選定システムの構築 |
山口県 | 土木建築部 道路整備課 阿部 雅昭 |
| 民間開発新技術発表 | ||
| 高含水比建設泥土のボンテラン工法でのリサイクル改良 |
建設業協会 中国ブロック協議会 | (株)砂原組 大内 甲一 |
| 溶融スラグの膨張抑制技術 |
(社)日本土木工業協会 | (株)間組 佐々木 肇 |
| 時間分割多重化によるFBG 光ファイバセンサを用いたモニタリング |
(社)日本土木工業協会 | 飛島建設(株)/ 復建調査設計(株) 田村 琢之 |
| 遺伝子解析技術を用いたゲンジボタルの地域集団構造の解明 |
(社)建設コンサルタンツ 協会 | 中電技術コンサルタント(株)増本 育子 |
| Slope Doctor -老朽化したモルタル吹付法面の維持管理マネジメントシステム- |
(社)全国特定法面保護 協会 | 日特建設(株)山西 霜野子 |
| 活用後の新技術・新工法工事事例発表 | ||
| 下水道管渠の更生工法について |
下関市 | 下水道部 工務課 藤谷 英樹 |
| 技術開発支援制度による研究発表 | ||
| 造粒石炭灰の地盤材料としての利用技術の開発に関する研究 |
山口大学大学院 | 理工学研究科 兵動 正幸 |
| 技術開発支援制度による研究開発課題への照会等の窓口は、(社)中国建設弘済会(TEL082-221-6462)となっています。 | ||
中国地方建設 技術開発交流会 資料
※ 各年度をクリックすると、過去の交流会が表示されます。